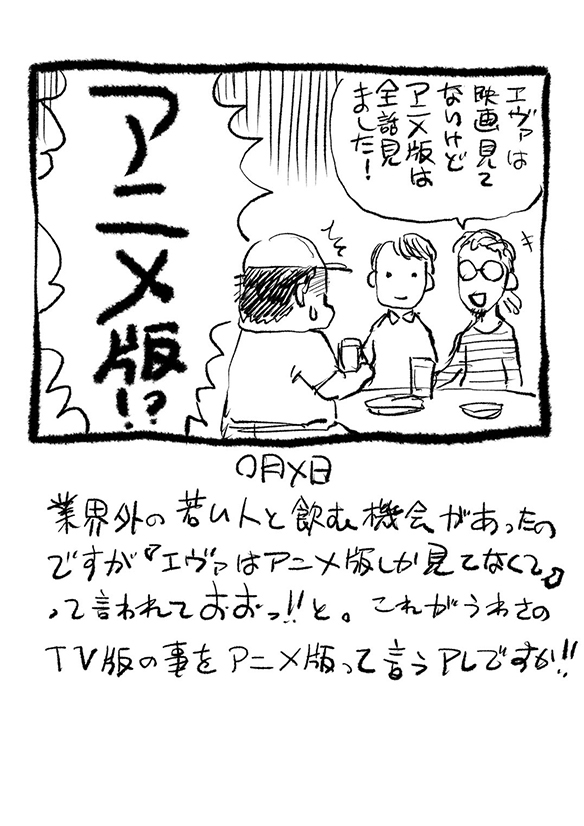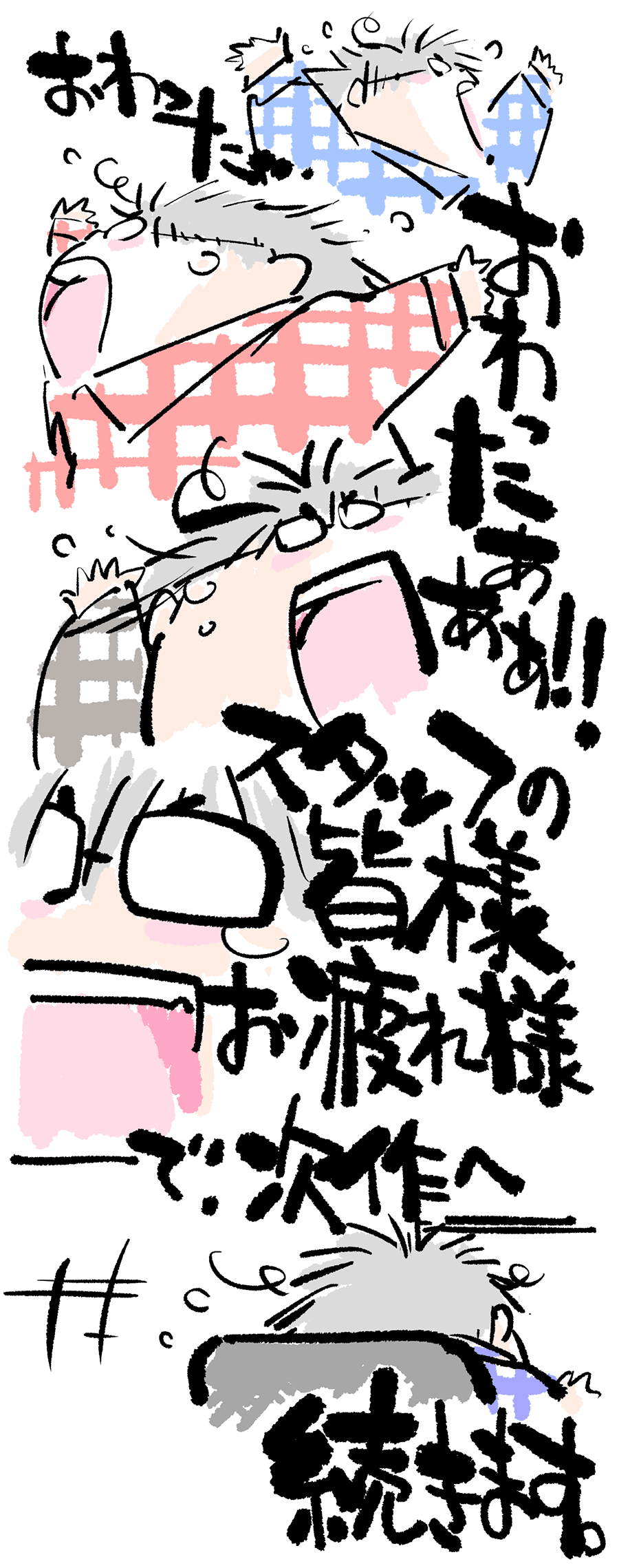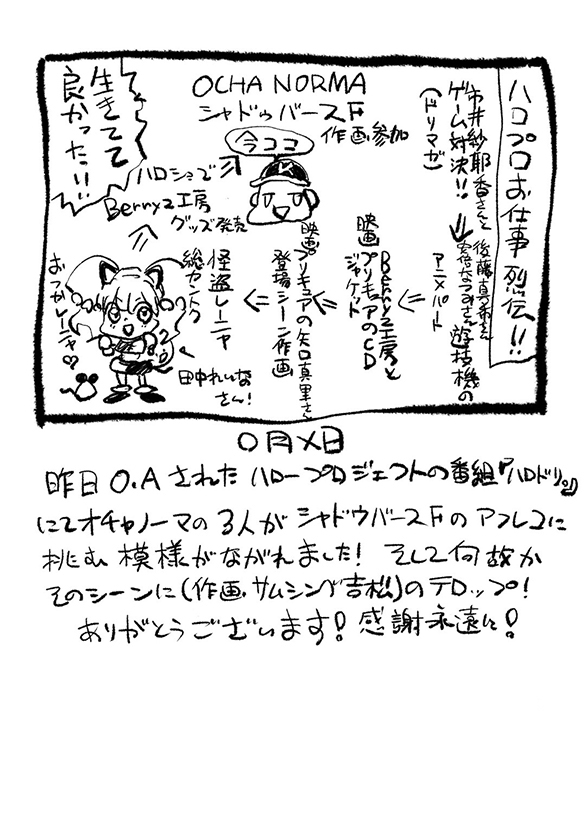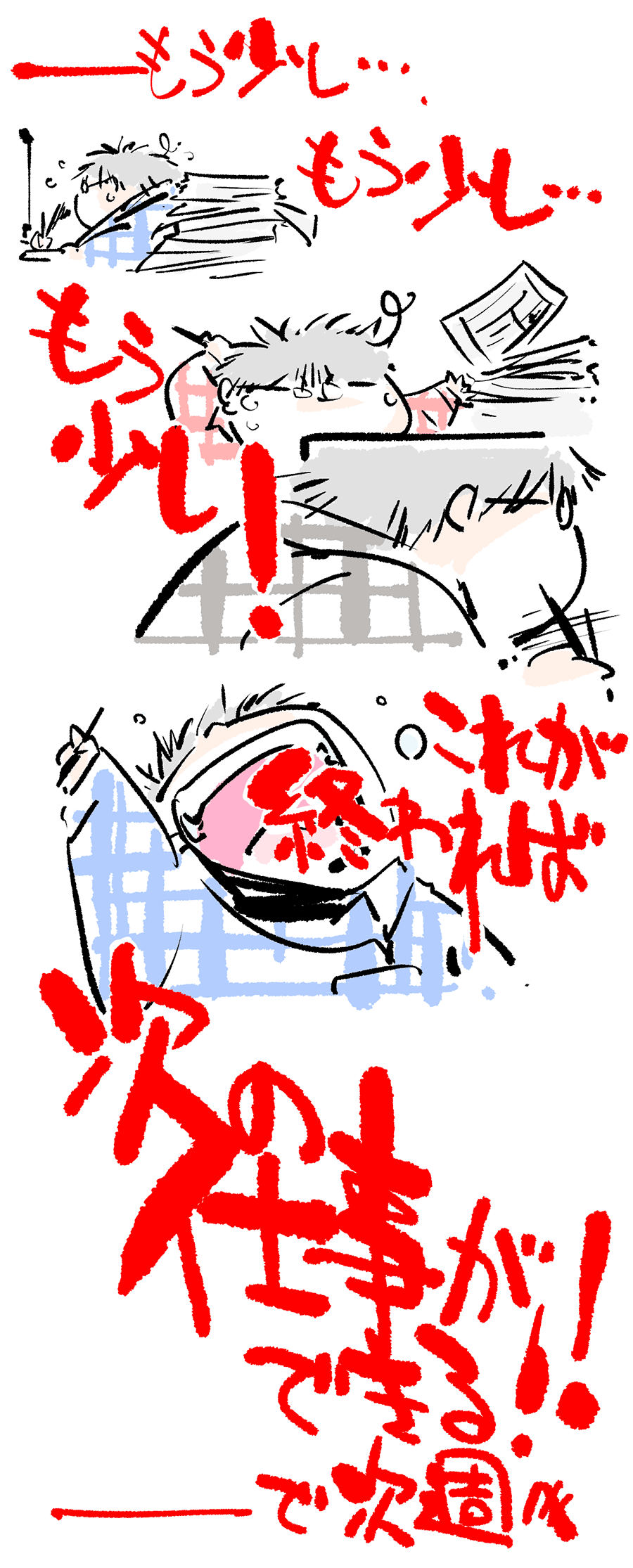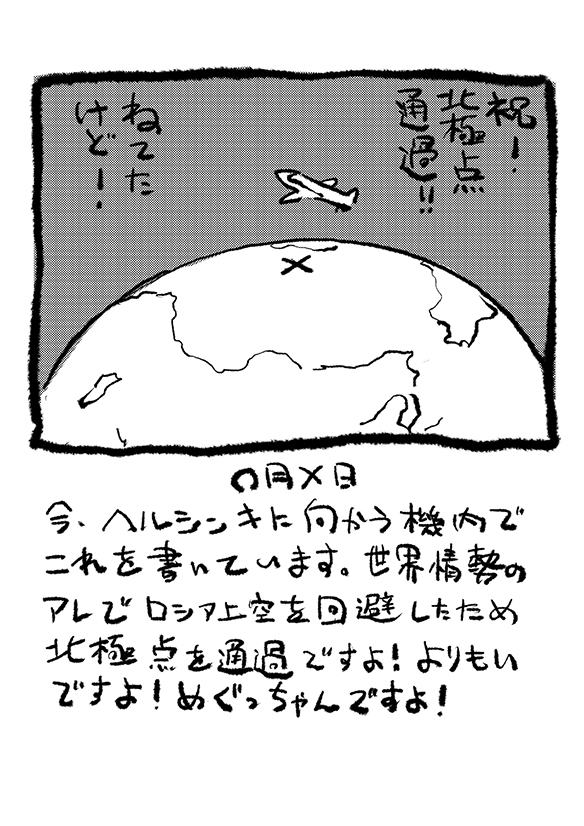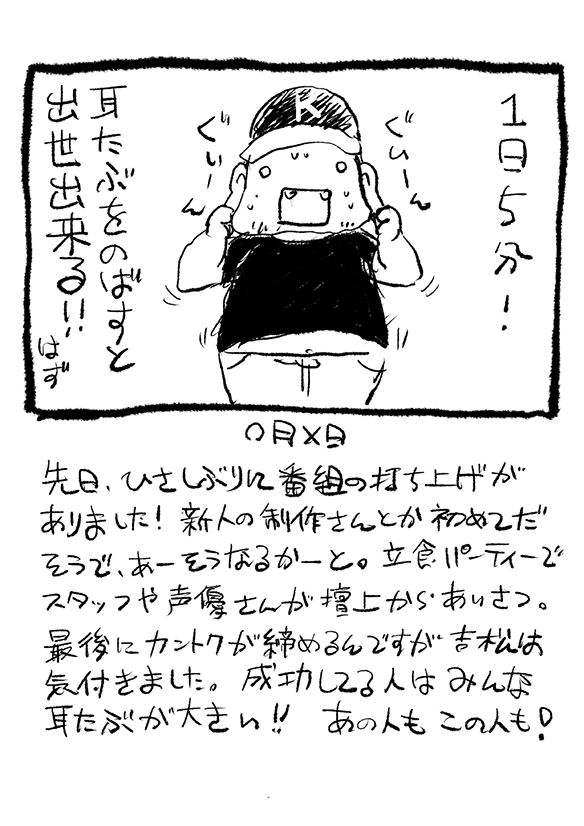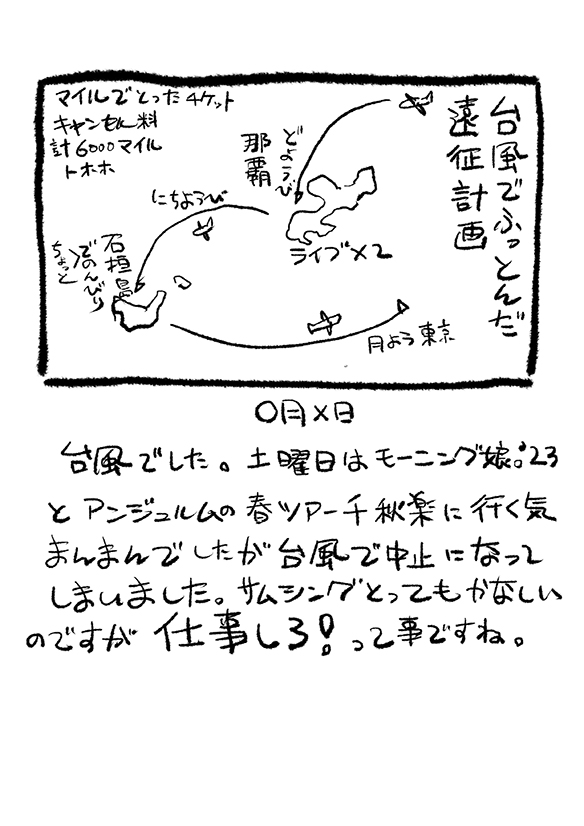小黒 次が『魔女見習いをさがして』(劇場・2020年)です。こちらは佐藤さんが取材で話をされた回数も多いと思います。
佐藤 『魔女見習い』ですね。
小黒 僕のほうで説明をすると、最初に『どれみ』の新作を作るという話があって、小説版『おジャ魔女どれみ16』や『おジャ魔女どれみ17』を映像にする可能性もあった。でも、そうではないということで、かつて『どれみ』を観ていた女の子達の話になった。ということで間違いないですね。
佐藤 そうですそうです。
小黒 佐藤さん自身は、『どれみ』の新作を作るということ自体についてはどうだったんですか。
佐藤 「20周年なので映画やりたいんです」って聞いた時には、やっぱり「誰がどんな『どれみ』の映画を観たいんだろう」ということが掴めなくって、ぼんやりと返してたんですよ。小説が展開していることも知らなかったんですよね。だから、小説の映画化をやるのかなと思ったけど、それが求められているかどうかを自分では判断しきれずにいたんです。そうしたら『どれみ』ファンだけじゃなくて、もうちょっと裾野を広げてほしいっていうオーダーが上のほう(東映アニメーションの髙木勝裕社長)から来て、「『どれみ』を子供の頃に観ていた大人、アニメーションに背中を押されている大人の話」という切り口が出てきた。それで「あ、それならやれそうだな」と思ったのは覚えてるね。
小黒 新文芸坐のレイトショーでトークしてもらった時も聞きましたけど、もうちょっとリアル寄りの世界観なり演出なりで作る可能性もあったわけですね。
佐藤 あった。あったし、コンテに入る前になっても、どうしようかなあと思ってた。最初に上がってきた谷(東)さんのコンテは若干リアル寄りではあったんですよね。その後、五十嵐のコンテが上がってきたのを見て、谷さんも「ああ、こっちだった」とコンテを修正してね。僕も含めてみんなで「そうだな。こっちだな」って思って、腹が決まりましたね。
小黒 補足すると、五十嵐さんはTVの『どれみ』と同じような、ちょっとギャグがあったりする楽しい感じの絵コンテを上げてきたわけですね。
佐藤 そうですそうです。『どれみ』でよくやっていた「崩し」を大量に使う演出になっていた。
小黒 どれみちゃん達に憧れた人達がいる世界は、もっと現実に近い世界を作るのが定石なんだけど、彼女達がいる世界も、マンガ的な楽しい雰囲気の、ちょっと理想化された世界である。その世界の挫折や悩みはややリアルなものなんだけど、テイストとしては楽しい感じでいいんではないかとなっていったわけですね。
佐藤 『どれみ』の世界観と、空気が繋がってる感じにしていこうということだね。
小黒 正しいかどうか僕にはまだ分かんないんですけど、確かに映画を観てる間に『どれみ』を観てる気分にはなりましたね。
佐藤 最終的には、そうなってもらえばいいんじゃないのっていう感じでいるので(笑)。
小黒 最後、どれみちゃん達が出る必要性はあったんですか。
佐藤 店の中にいるやつね。でも、あそこしか、どれみの出る場所はないんだよね。
小黒 そうですね。
佐藤 僕は「魔法は現実にはなかったよ。なかったけれども明日から生きていけるよね、君達」という文脈を考えていたんです。だけど、それだと最後のどれみのシーンはあっちゃダメなんです。
小黒 あっちゃダメですよね。
佐藤 でも、イベントに行くと、最前線の席に座っている大人の女性達の目が凄くキラキラしてるわけですよ。それは『プリンセスチュチュ』のイベントの時もそうでした。この気持ちは肯定してあげるべきものだと思ったんですよ。
だから「魔法なんかない」じゃなくて「魔法はなかった。でもね、あるかもしれないよ」という映画にしていくわけですよ。そうすると『どれみ』が好きだった子供の時の自分を肯定することになるんでね。そういう流れだと、どれみ達が空を飛んでいくっていうビジュアルが力を持つことになる。この映画を観ることが、明日も生きる力に繋がるはずだ、という感じ。
小黒 3人の悩みが一段落した時に、どれみ達の姿を見るからいいわけですね。「つらい現実の中で私達は生きていて、魔法なんかなかったんだ」と思っている時に、どれみ達に会うとつらいじゃないですか。
佐藤 つらいし、もう見たくないになっちゃう。
小黒 彼女達も自分達の理想に一歩近づいて、現実世界の中で自分達の魔法を手に入れた上で、どれみちゃん達に会うと、そんなにおかしくはない。
佐藤 あそこにいる3人の子供の姿は視聴者、観客の一人一人というつもりなので、一緒に会ってる感じなんですよね。「映画のスクリーンにいるどれみ達に、観客の私も3人と一緒に会っている」。そして、飛んでいく気分で終われるんじゃないのかなって。ただ、映画館から出た後も余韻として残ってて、明日会社を辞めようって思われるかもしれないけど (笑)。自分の未来を信じてみたい気持ちになる人だっているかもしれないじゃんということですね。
小黒 ところで、『どれみ』を好きな人達をご自身で描くのは、照れ臭くなかったですか。
佐藤 それは最初からずっとそうなんだけど(笑)。「君達は『どれみ』が好きなんだろう」という映画を自分で作るのはやっぱ難しいよね。でも、そう信じないと描けないから。
小黒 最新作が『ワッチャプリマジ!』(TV・2021年)ですね。これはどういった取り組みなんですか。
佐藤 筐体ゲームのアニメなので、新しいビジネススタイルに取り組むのが面白い作品ではあります。これを楽しむ女の子達の年齢は『プリキュア』を観ている子達と同じくらいないんだけれども、遊び方が大きく違うからね。「おもちゃを買って遊ぶ」じゃないところが、難しくもあり、面白くもあり、ですね。
小黒 なるほど。
佐藤 『HUG』の時と同じように、脚本の坪田(文)さんが、お話の軸を作ってくれていて、個人的にも好きな話なので、演出的には楽しめるかなと思っています。
小黒 佐藤さんは、これから映画ばっかり作っていくのかと思いました。
佐藤 いや、映画が続いたのはたまたまだから。ビジネスのスタイルがそうなっていて、TVよりも映画のほうが制作をスタートさせるハードルが低かったから。これから、配信物ばかりやってるという時代になるかもしれないけど。
小黒 いやいや、もうなってますよ。配信される作品ばかり作ってる人もきっといますよ。
佐藤 その時代その時代の中でやってるだけなので。まあ、相変わらず映画は苦手だなと思ってる感じがありますけどね(笑)。
小黒 今でも映画は苦手なんですね。
佐藤 映画のスクリーンでなにかやるのは難しいと思ってます。やっぱりTVが一番自分に合ってるなっていうのは、今回『プリマジ』をやりながら思っていますね。
●イントロダクション&目次
座談会参加者:板垣伸(アニメ監督)、小黒祐一郎(編集長)、松本昌彦(編集者)
小黒 『いせれべ(異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する)』だと、エンディングのクレジットに「原画」「動画」の役職がなくて、「作画」「原動画」の役職があるよね。アニメーターの仕事内容が通常の作品と違うの?
板垣 作画監督が修正を入れたラフを、第二原画を兼ねて動画の線でクリンナップしてしまうんです。そういったショートカットが、うちのやり方なんですよ。第二原画の作業もしているので、役職を動画でなく、原動画にしています。
小黒 第二原画をやる人は必ず動画もやるの?
板垣 ある話数でたまたま第二原画だけをやる場合もありますが、基本的には第二原画と同時に動画、それから、仕上げもやってもらっています。場合によってはアニメーターが背景も描きます。
小黒 それは凄いなあ。「作画」は?
板垣 ラフ原画だけを描いて、第二原画を任せるのが「作画」です。第二原画を担当しない代わりに、カットのあがりをチェックすることになっています。それから担当カットが少なかった作監を「作画」としてクレジットすることもあります。
小黒 それは社内スタッフのやり方だよね。参加しているのは全員が社員なの?
板垣 うちの会社(ミルパンセ)は基本的に社員雇用なので、社内のスタッフは社員ですね。結構な分量を社内生産でやっています。
小黒 「やろうと思えば、作り方そのものを変えられる」というのはそういうことなね。
板垣 昔の話になりますけど、パソコンとかに興味を持ってる友達が「コンピューターを使えば、漫画家とアシスタントぐらいの人数でアニメが作れる」と言っていたんですよ。自分達はアナログのアニメを目指してたから、彼に反発したんですよ。「アニメって、もっと大きいもんだ。みんなで作るもんだ」と言ったんです。でも、今は彼の説を推してるんです。多分ね、漫画家とアシスタントぐらいの人数で作った方が、人類の精神衛生上いいです。
小黒 ふむふむ。
板垣 クリエイターになりたい人と、作業者になりたい人がいるんですよ。うちらが若かった頃って、みんながクリエイターを目指していた。例えば、監督を目指すとか、キャラクターデザインや総作監を目指すとか。それについてこられない奴は切り捨てられるのではないかという空気だったんですよ。
小黒 わかるわかる。
板垣 要は「クリエイターになりたいんじゃないのか? 作業者でいいのか?」という意識があったんです。だけど、働き方改革で1日8時間労働と週休2日制を肯定するなら、作業者の存在を認めざるをえないんですよ。
小黒 そうなんだろうね。
板垣 今は「自分は作業者でいいから、1日8時間で帰って、家でゲームやってたいんだよ」という人達もいるわけです。だとすると、仕事を切り分けて、月給や時給をもらってやるような作業内容にしていかないといけないわけです。それは漫画家とアシスタントの、アシスタントなんです。クリエイターになりたい人もいるだろうし、クリエイターを求めている会社もあるんだろうけど、自分はそうでない人がいてもいいと思っています。
それが、これからの働き方でいいと思っているんです。どうなんです? アニメスタイルさんは、それができてるんですか。
小黒 昔に比べればね。今は、みんな、家に帰ってるよ。
板垣 ああ、帰ってます?
小黒 うん。
板垣 何人ぐらいなんですか、アニメスタイルは?
小黒 社内の編集スタッフは、僕を入れて5人かな。今は編集業務をしている人で出勤してるのは3人しかいないから。
板垣 リモートですか。
小黒 そうそう。家でできる作業は家でやる。
松本 会社で作業をしているアルバイトの人もいるから、3人ってことはないんじゃないですか。
小黒 ああ、そうか。もう少しいます(笑)。松本君も基本は自宅作業だから、板垣さんのコラムの原稿が届くのが、どんなに遅い時間になっても大丈夫です。
板垣 いや、遅い時間に原稿を送ったりはしてないですよ。
松本 (笑)。
板垣 でも、この連載も10数年やっているでしょ。
小黒 長いよねえ。
板垣 長いことやっているから、自分も変わりましたよ。一瞬の諦観があって、諦観と期待感がいい感じにバランス取れてるなあと思ってて。
小黒 昔の板垣さんはもっと脂っこかったね。
板垣 そうでしょ。あの頃に比べると、色んなものがどうでもよくなった(笑)。ただ、作品を作るのは本当に面白いんで、その面白さを伝えたいなあと思っているんです。クリエイターにならなくても、クリエイティブな現場にいられる。うちの会社で「人生の寄り道としてアニメの仕事をやってみたい」という人を受け止められるにしたい。そういうもの作りに参加することの面白さを伝えられる作品ができたらいいなあと思いますね。
小黒 「人生の寄り道」というのは、一生の仕事にするわけではないけれど、ということね。
板垣 そうです。自分は原作をいただいて作るのも嫌じゃないんですよ。ありがたいことに、このあとも2本ぐらい、企画が控えてるんです。だけど、そろそろ短いものでもいいので、自分1人で作ってみるとか、自分とアシスタントぐらいの規模で作れるようなものに手つけたいなあと思ってきた感じですかね。
小黒 オリジナルって事?
板垣 そうですねえ。自分が惚れ込んだ原作でもいいんですけど、でも、オリジナルが一番手っ取り早いですよね。
小黒 そうだね。
板垣 軽いアニメを作ってYouTubeとかで流すぐらいのところから、探るべきかなあと思っています。
特別編・いきあたりバッタリ座談会(3)に続く
2022年12月18日(日)
入院11日目。「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 友の会」リーフレットの校正を進める。
配信で『LUPIN ZERO』1話と2話を観る。とにかく音楽がいい。『旧ルパン』の楽曲をリメイクして使っているのだ。『PARTIII』の後くらいに、この手法で『ルパン三世』のOVAをやってくれたら幸せだったろうなあ(『風魔一族の陰謀』にこの曲を付ければよかったと言っているわけではない)。『チェンソーマン』9話、10話、『モブサイコ100 III』10話を観る。スマホとイヤフォン(Bluetooth)の組み合わせで動画を観るのは1日2~3時間が限界か。慣れていないためか、普段の視聴よりもずっと疲れる。Kindleで「怪獣第8号」1巻から最新8巻まで読んだ。
2022年12月19日(月)
入院12日目。体調はよくなっているのだけれど、いつ退院できるのかはまだ分からない。酸素注入器を外すことになった。看護師さんが酸素注入器を付けないでトイレまで歩いた時の血中酸素を計りたいというので、血中酸素を計る機器を付けて、トイレの前まで行って戻る。
仕事のお供は配信の『GHOST IN THE SHELL』。
トークイベント「第198回アニメスタイルイベント 作画を語る上で重要なこと」を開催。一部と二部を配信で見る。自分が出ていないアニメスタイルイベントを配信で観るのも不思議な気分だった。
2022年12月20日(火)
入院13日目。21日に退院できることが決まった。担当の先生に病状のこと、今後のことを説明してもらう。入院中の洗濯物を宅急便で自宅に送る。
『異世界おじさん』10話を観る。エンディングで確認する前に坂井久太さんが作監だと分かった。『ポケットモンスター』の最終回も観た。「アニメスタイル017」のある特集の企画書を書く。
2022年12月21日(水)
入院14日目にして退院の日。深夜、配信で『ヤマノススメ Next Summit』最終回を観た。いい最終回だった。遂にここまできたか、という感じ。午前10時に病院の1階に行って会計をしてから、病室に戻る。病室で書類を書いて、退院の手続きは終了。病院から少し歩いて、山手線で池袋に。昼に自宅に到着。ワイフと話をする。午後から事務所に。Amazonから届いた段ボール箱等を片っ端から開封する。15時からZoom打ち合わせ。仕事でお世話になっている方とメッセージのやりとり。12月中に片づけなくてはいけない用事があったことを思い出す。いかんいかん。
二週遅れで『うる星やつら』のレイの初登場回を観る。改めて原作を読むと、あたるの母親がレイによろめくのが生々しい。今回のアニメ化ではどうするんだろうと思っていたのだけれど、やっていることは原作のママだけど、芝居等のニュアンスで生々しさを弱めていた。なるほど。
2022年12月22日(木)
退院してから2日目。散歩は少しだけ。ラジオ体操も休む。仕事に関しては調子が戻らず、作業が進まない。入院中のほうがスピーディーだった。「アニメスタイル017」関連の新しい企画書を書く。
現行の深夜アニメを次々に視聴。『ヒューマンバグ大学 不死学部不幸学科』はラスト4本くらいをまとめて観た。TOKYO MXの『新世紀エヴァンゲリオン』と『マジンガーZ』は2週分をまとめて観た。『エヴァ』の第拾壱話「静止した闇の中で」は当時の印象よりも異色作だ。情報量が多いし、シーンの数も多い。ネルフ内での人間の繋がりを肯定的に描いているのも新鮮。それはそれとして、第拾壱話、第拾弐話の感じがもう少し続いてもよかったなあ。
2022年12月23日(金)
退院してから3日目。朝の散歩を再開。久しぶりに雑司ヶ谷を歩いて、馴染みの猫に会う。ラジオ体操もやった。
TOHOシネマズ 池袋で「空の大怪獣ラドン」(4K)を鑑賞。この映画を最初に観たのは名画座だったか、ビデオソフトだったか。とにかく、過去に二度くらいは観ている。今回の4Kデジタルリマスター版は猛烈に映像が綺麗で、記憶にある映画とかなり違っていた。これは贅沢な感想なのだけれど、映像が鮮明になって、逆に「あれ?」と思うところがある。アニメの4Kリマスターで「背景が筆で描かれた画に見えてしまう」のと同じ現象が起きていた。例えば「ミニチュアで表現された戦車」が「戦車のミニチュア」になってしまったとか、そういうことだ。二週間入院して頭がスッキリしたためだと思うが、映画鑑賞に全くストレスがなかった。ずっとリラックスしていて、スルスルと映画の内容が頭に入ってきた感じ。
入院する直前に行った地元の病院に行く。11月25日の検査で大腸癌ではないと言われたが、あれは間違いで、やはり大腸癌だったそうだ。その病院では手術はできないので、先日まで入院していた病院で手術することになりそうだ(自分のために書いておくが、この辺りは当時のメモを頼りに書いていて、前後関係が怪しい)。腎臓癌に続いて大腸癌だ。
病院の待ち時間に「樋口真嗣特撮野帳 -映像プラン・スケッチ-」に目を通した。とてもいい本だ。収録されている資料も素晴らしいいんだけど、「本」としていい。装丁、本文デザイン、判型に対する厚み、そのいずれもがイケている。解説、キャプションが手書きなのもいい。
現行の深夜アニメを片っ端から観る。『ポケットモンスター 遥かなる青い空』はリアルタイムで視聴。よかった。先週までやっていたシリーズの続きではなく、1月から始まるシリーズのプロローグでもなく、『ポケットモンスター 遥かなる青い空』というタイトルの単独作品で、監督は湯山邦彦さん。1月から始まるシリーズが完結したところで、全シリーズ中における『遥かなる青い空』の位置づけが見えるのではないだろうか。
2022年12月24日(土)
退院してから4日目。ワイフと近所のフルーツカフェに行く。24日の午前中の段階で、小黒家のクリスマスはピークに達した。肉好きに分かりやすく説明すると「サーロインステーキ500グラム」とか「塊肉をキロ単位で注文」とか、そういうレベルの店だった。すいません。舐めていました。午後はゆるーくデスクワーク。
2022年12月11日(日)
入院4日目。自分は会場に行けなかったが、この日は新文芸坐で「湯浅政明の超傑作『マインド・ゲーム』と『犬王』」を開催した。トークのゲストは湯浅さんだ。僕が聞き手を務める予定だったが、岡本敦史君にやってもらうことになった。トークの前に湯浅さんとメッセージのやりとり。「小黒さんはどんなことを訊くつもりだったんですか」という質問をもらって答える。
引き続き、病室でできる編集作業を進める。Wordでないと開けない書類が届いた。何故かMacBookにWordをダウンロードをすることができなかったので、iPad Proで開く。
Kindleで「チ。-地球の運動について-」を1巻から最終巻まで読む。これはいつか読もうと思って買って、読んでいなかったマンガだ。
2022年12月12日(月)
入院5日目。レントゲンを撮るために病院の二階に。二階には外来の患者も大勢いて、数日ぶりに社会に触れた気がした。この日はレントゲン以外にCTスキャンがあり、それとは別にハンディタイプの機器を使った検査が二回。来年以降に出版する書籍のために資料について、ある制作会社からメールが届く。ありがたい提案だったけれど、入院中なので今は進めることができない。
Kindleで「ローカル女子の遠吠え」1巻を読み始める。消灯後、堺三保さんと「KISS AND CRY 資料集」の英題についてメッセージでやりとり。
2022年12月13日(火)
入院6日目。入院してから初のシャワー。沓名君、夏目さんとLINEでやりとりして、僕抜きでイベントを開催してもらうことになった。小黒が不参加でも開催したほうがいいというのは、会場側の意見だった。
2022年12月14日(水)
入院7日目。Kindleで「宝石の国」特装版に目を通す。担当の先生に「明日の検査の結果がよければ退院が見えてくる」と言われる。「退院できる」ではなくて「退院が見えてくる」なのね。この病院には1階にセブンイレブンがある。看護師さんにセブンイレブンの利用について質問したところ、移動していいのは病室がある階のみとのこと。池袋のジュンク堂の地下に、買い損なっていた「シン・エヴァンゲリオン劇場版 アニメーション原画集 下巻」があったのを思い出して、メールで、事務所スタッフに購入を頼む。
夕方から夜にかけて、やることが多かった。編集作業が進行中の書籍についても、それ以外も。
病室の洗面台で歯を磨いていたら、看護師さんが飛び込んできて「大丈夫ですか!」と訊かれた。心電図の数値が急に上がったらしい。自分は歯を磨く時に息を止める癖があって、そのせいで数値が上がったらしい。ナースステーションで心電図をチェックしてくれているのが分かった。
2022年12月15日(木)
入院8日目。血圧検査の結果、治療中の病気とは別に、肝臓に問題があるかもしれないことが分かり、その検査をした。看護師さんに1人でセブンイレブンまで行っていいと言われて、早速行ってみた。何かを売っている店に行ったのが久しぶりで、大袈裟なことを言うようだけど、店内に並んだ商品がキラキラしているように見えた。隣にあるユニクロも物質文明の塊に見えた。セブンイレブンで購入したのはスリッパ、イヤホン(有線)、ボールペン、ペットボトルの「お~いお茶 濃い茶」。イヤホンは病室での動画視聴用に買ったのだけど、使ってみたら音がこもっている。これはきびしいかなあ。濃いお茶は最初の数口の味が異様に濃かった。入院してから薄味のものばかり食べていたので、そう感じたのだろう。
2022年12月16日(金)
入院9日目。肝臓に問題なかったけれど、腎臓に問題があるらしいことが分かる。どうやら腎臓癌であるらしい。今の治療が一段落したら、改めて検査をして手術をすることになるそうだ。癌か。遂にきたか。正直に言うと、ショックだった。悔いを残さないように、これからやることの順番を考えたほうがいい。自分が出しておきたい本はなんだろう。その優先順位は? 出版だけでなく、書きたい原稿は書けるうちに書いておいたほうがいいな。最初に書かなくてはいけない原稿はなんだ? そんなことを考えると、どんどん気持ちが重たくなっていく。
進行中の治療に関しては、この日、胸に付けていたコードを外してもらう。残るのは点滴の管と酸素注入器だ。引き続き、病室でできる範囲で仕事を進める。Kindleで「名探偵コナン」を97巻から読み始める。この辺りは、既にアニメで大体観ているなあ。「ラディカル・ホスピタル」の読んでいなかった巻を読む。病院で読むと臨場感が倍増してしまい、気持ちが入りすぎてしまうのが分かった。一冊だけ読んで読むのを中止する。
2022年12月17日(土)
入院10日目。MacBookにMicrosoft365をインストール。病院内のセブンイレブンとユニクロで買い物。スマホとイヤホン(Bluetooth)の組み合わせで配信のアニメを観る。入院してから、アニメを30分まるまる観たのは初めて。担当の先生にもう少しで酸素ポンペがいらなくなるはずだと言ってもらう。それから、なるべく歩いたほうがいいそうだ。と言っても、歩いていいのはセブンイレブンまでなんだけど。
数土直志さんの「日本のアニメ監督はいかにして世界へ打って出たのか?」をKindleでざっくりと読む。ドラゴンウォークで、強敵モンスターの竜騎将バラン(レベル30)を倒した。歩くことができないので、ドラゴンウォークでできるのは強敵モンスターと、どこでもメガモンスターくらいだ。