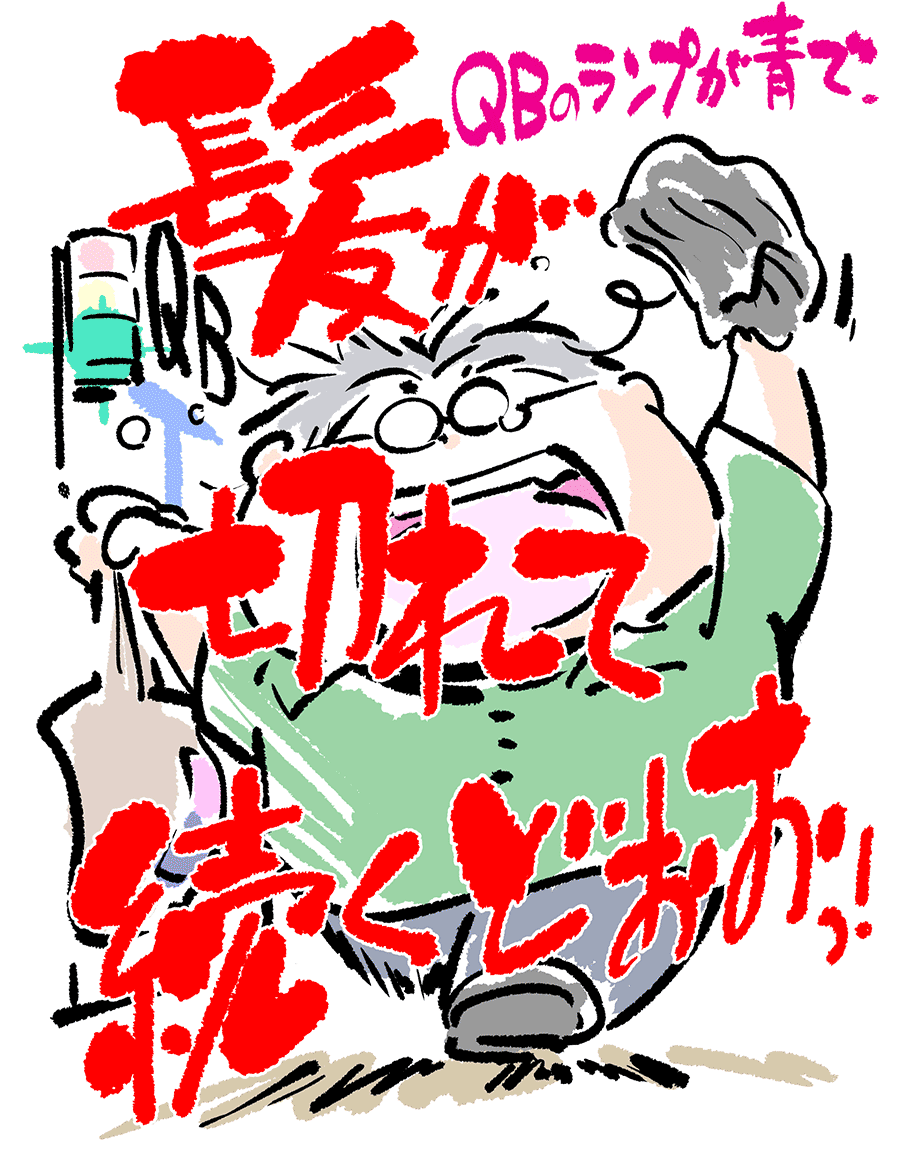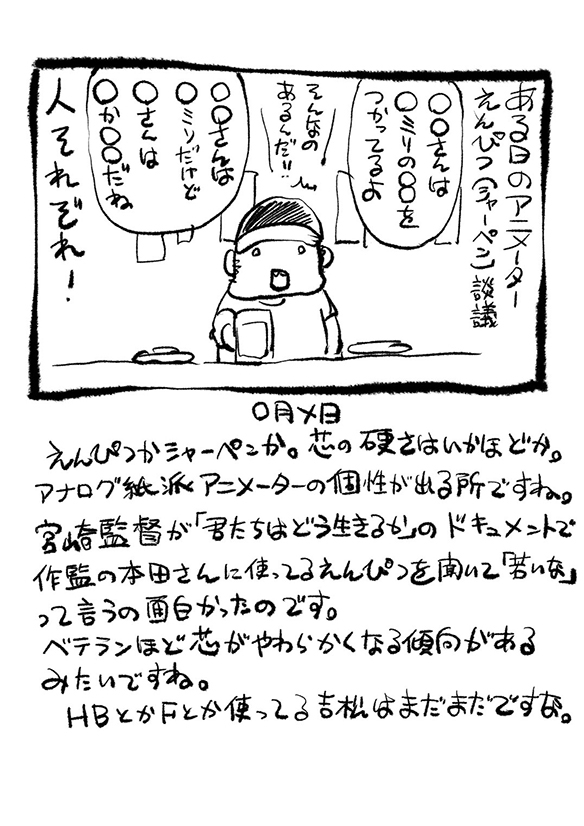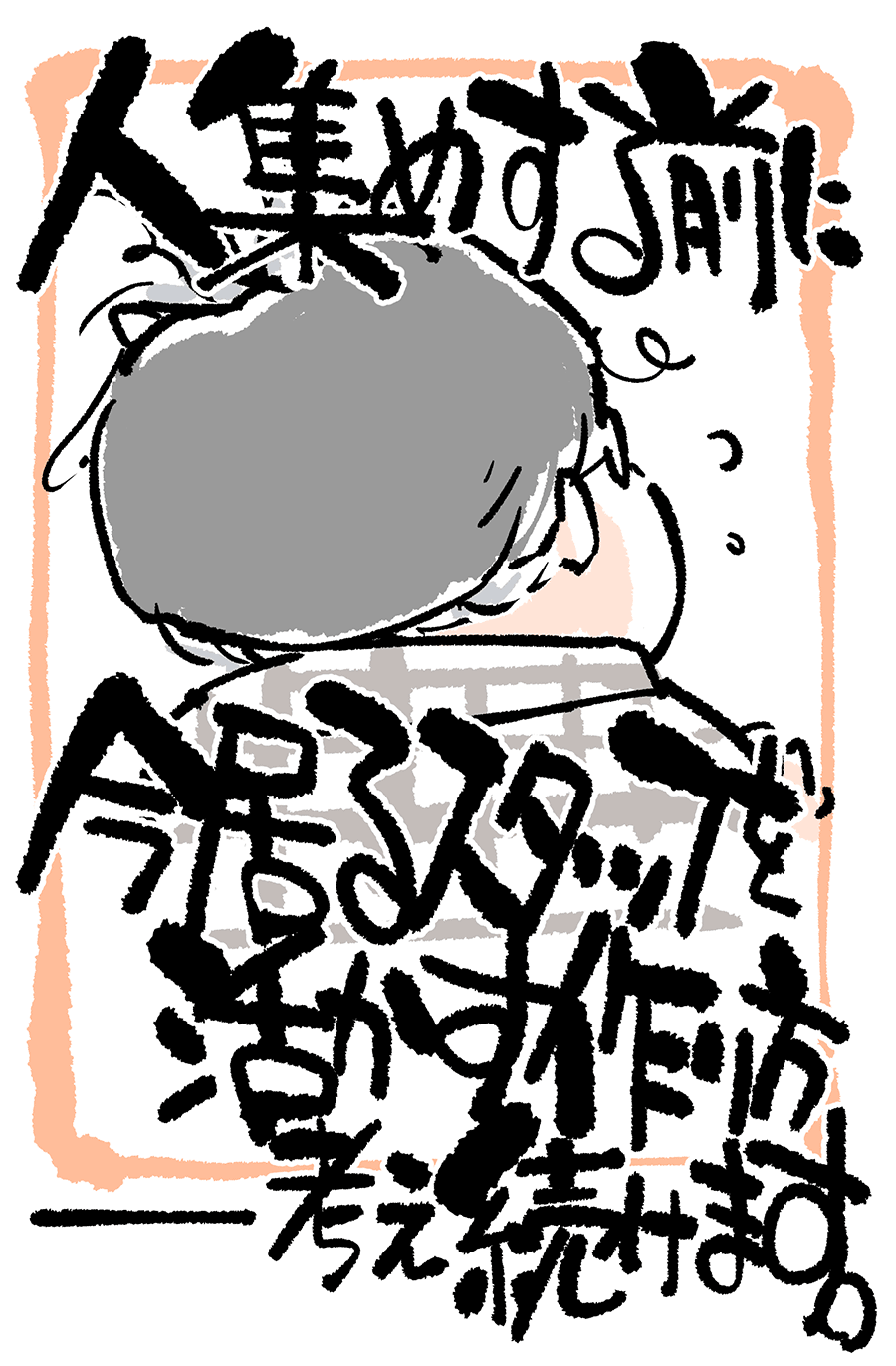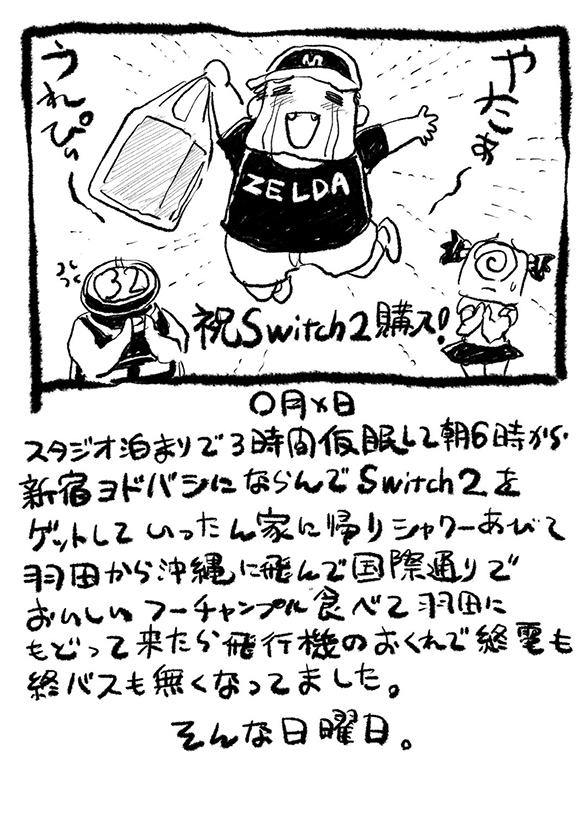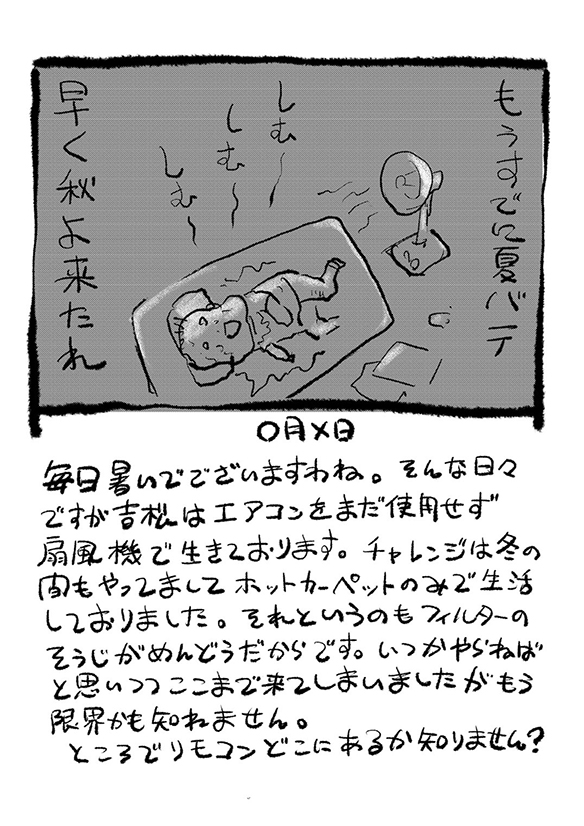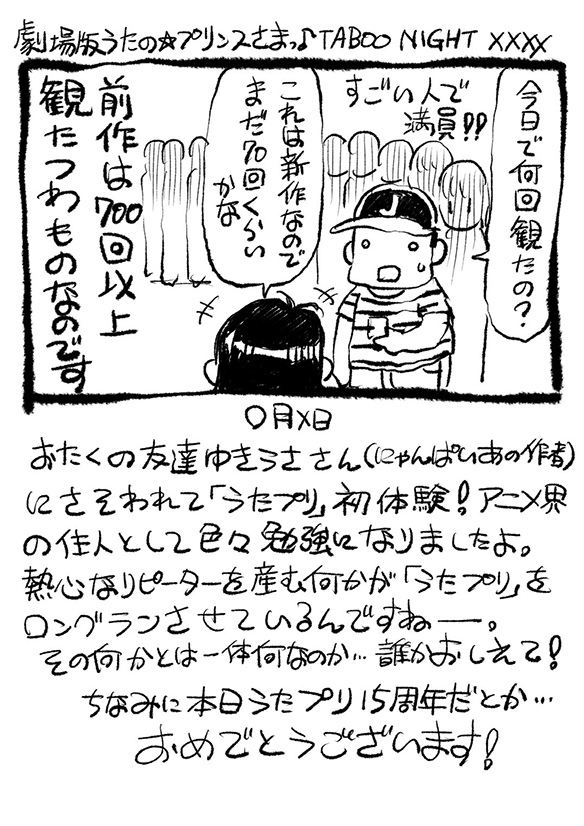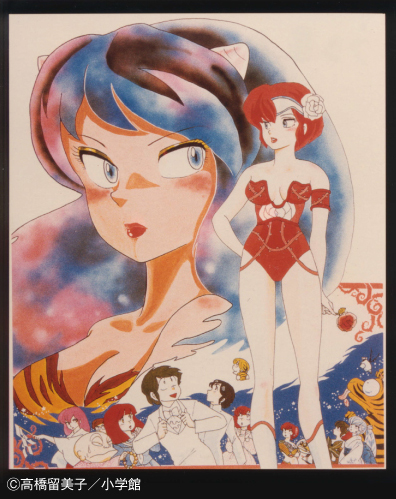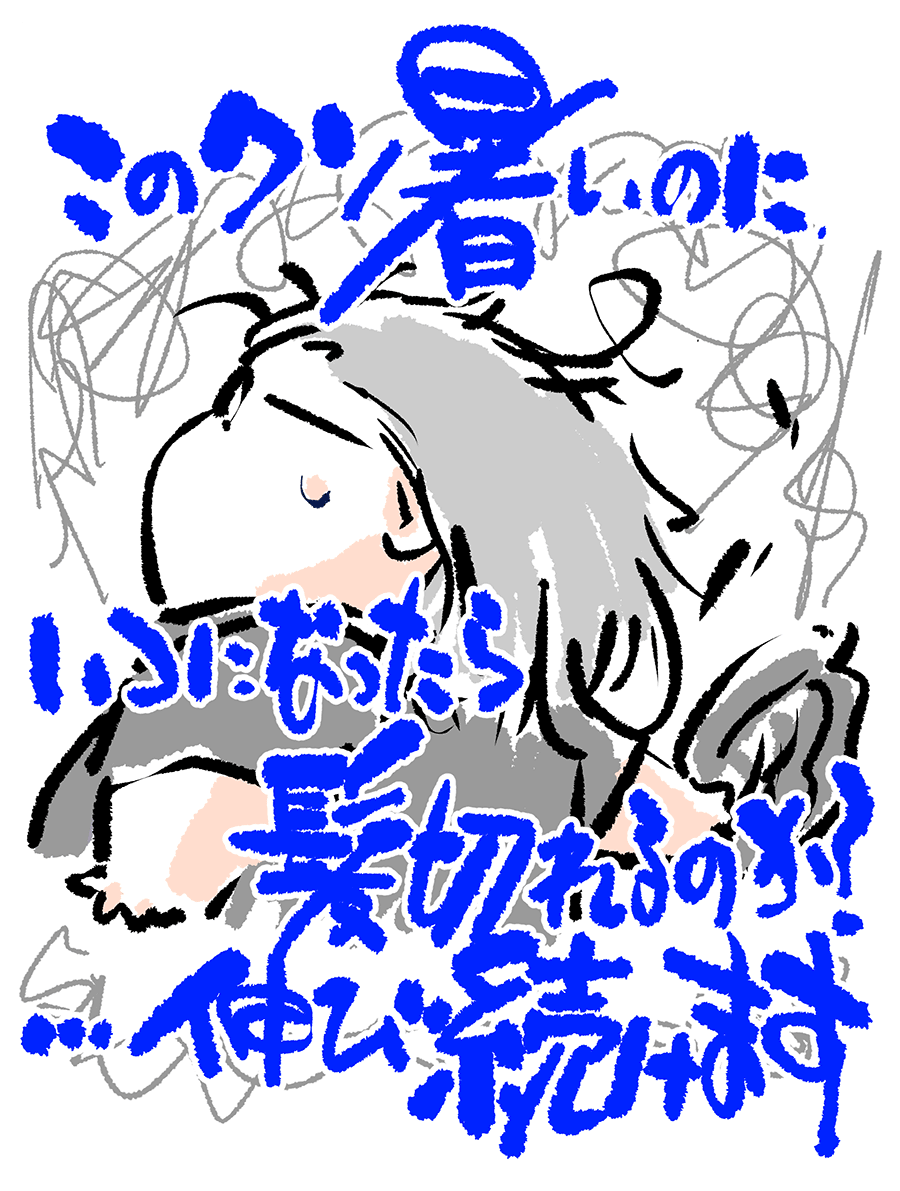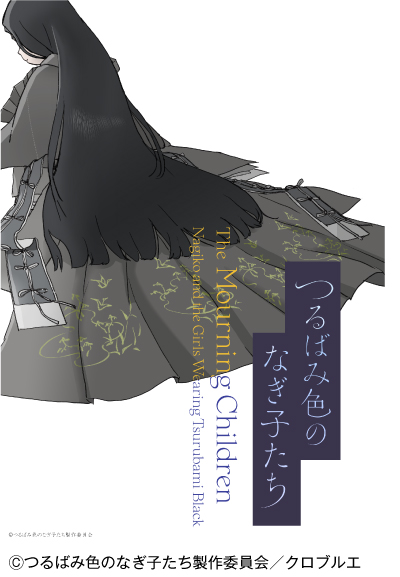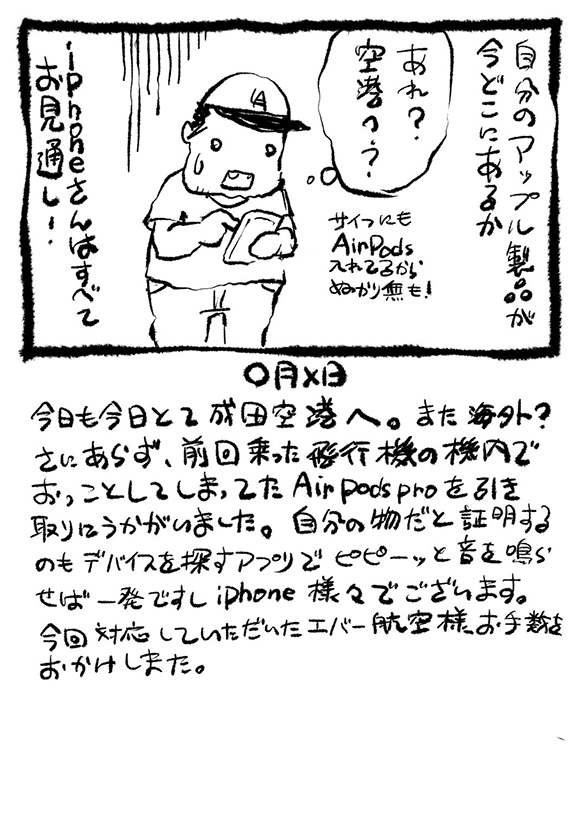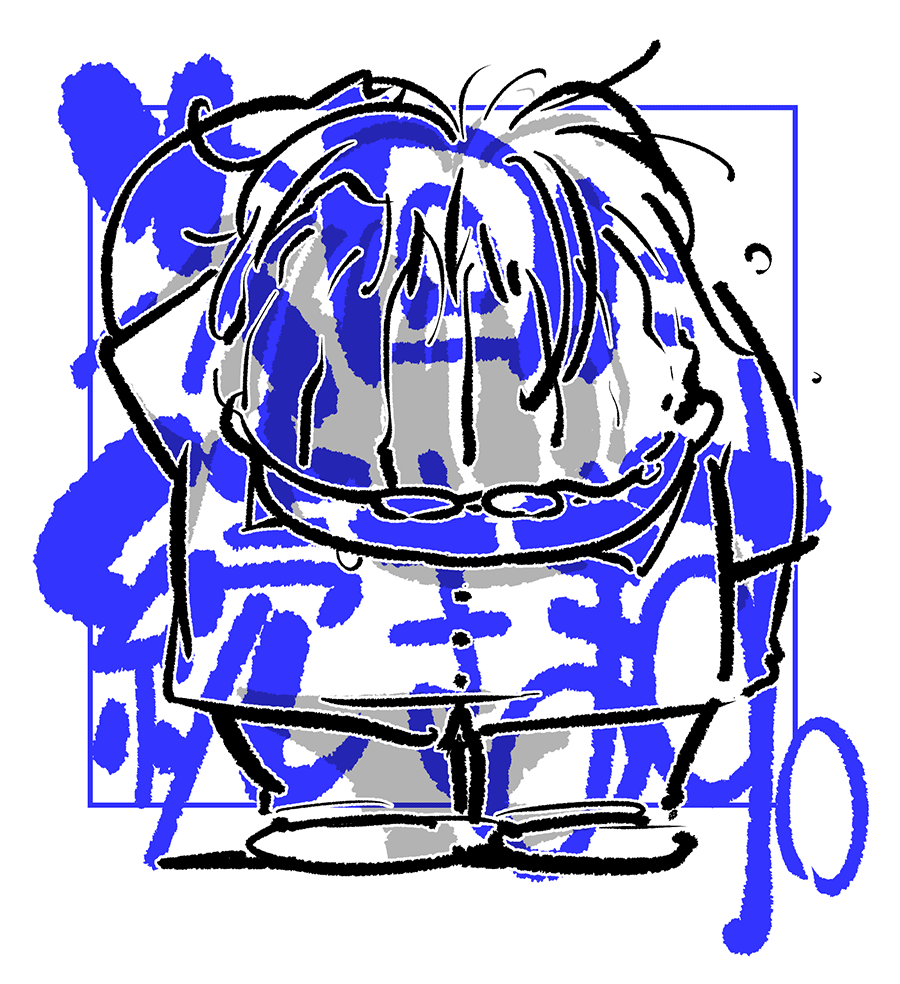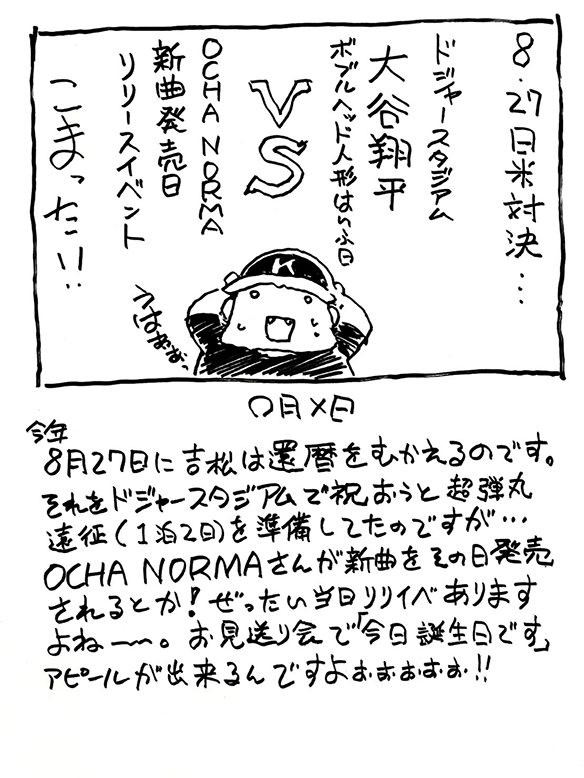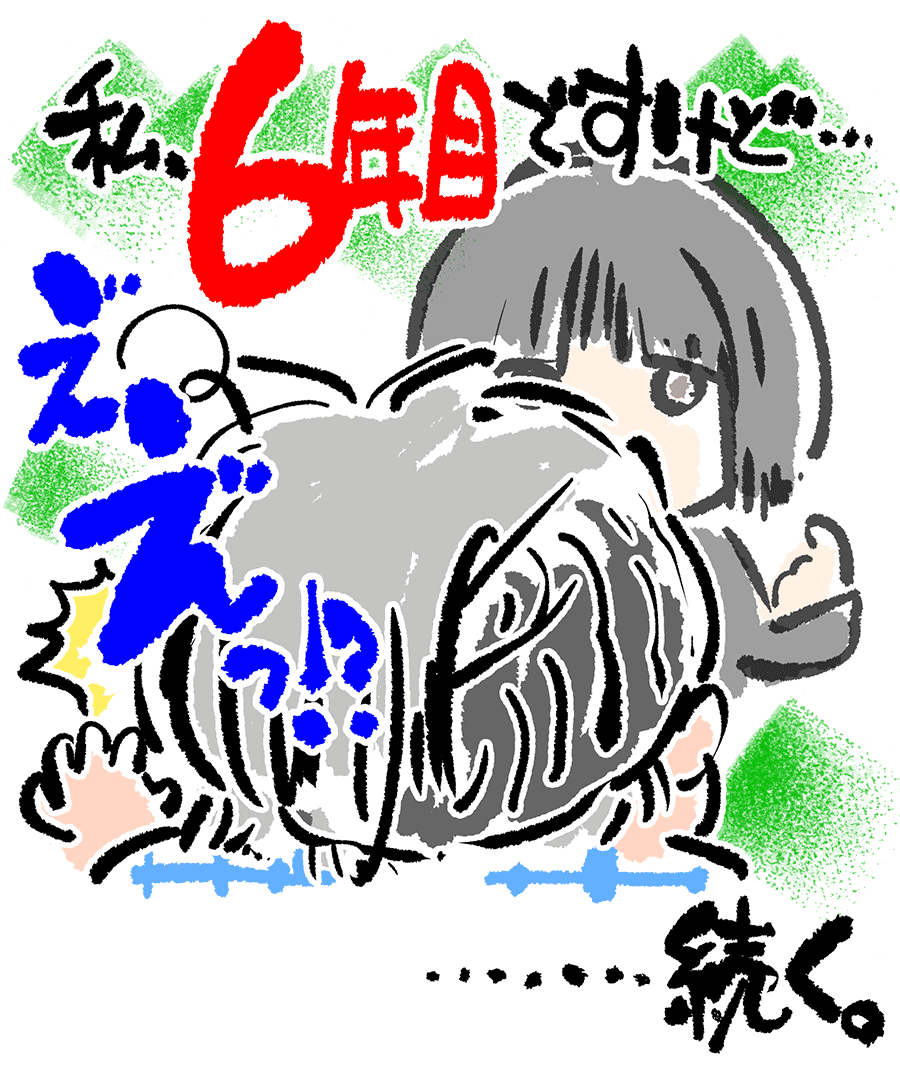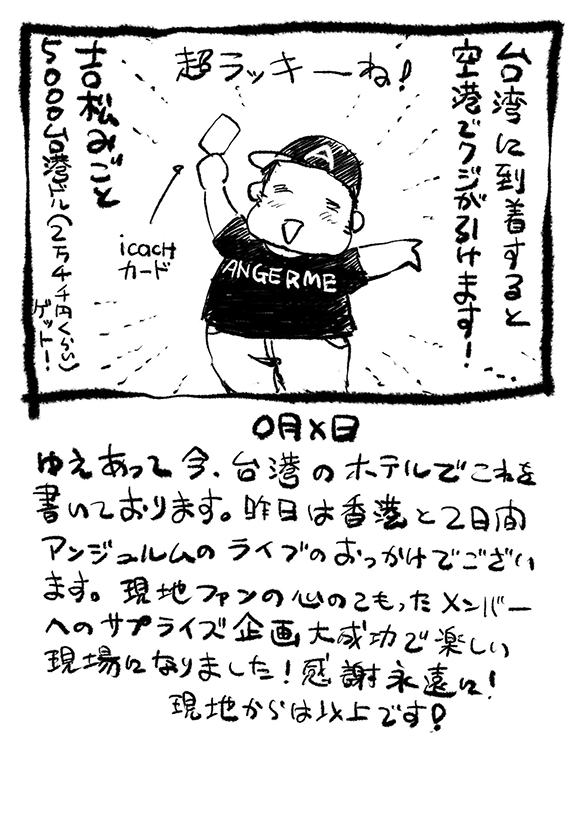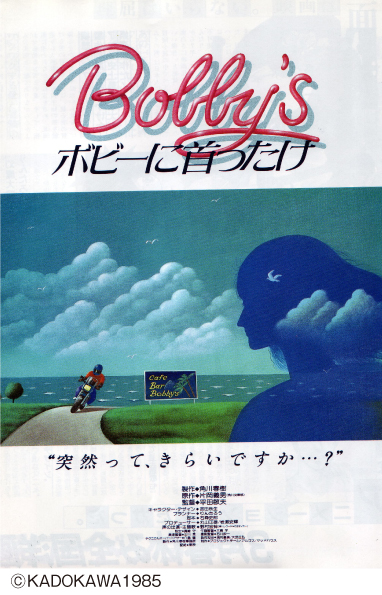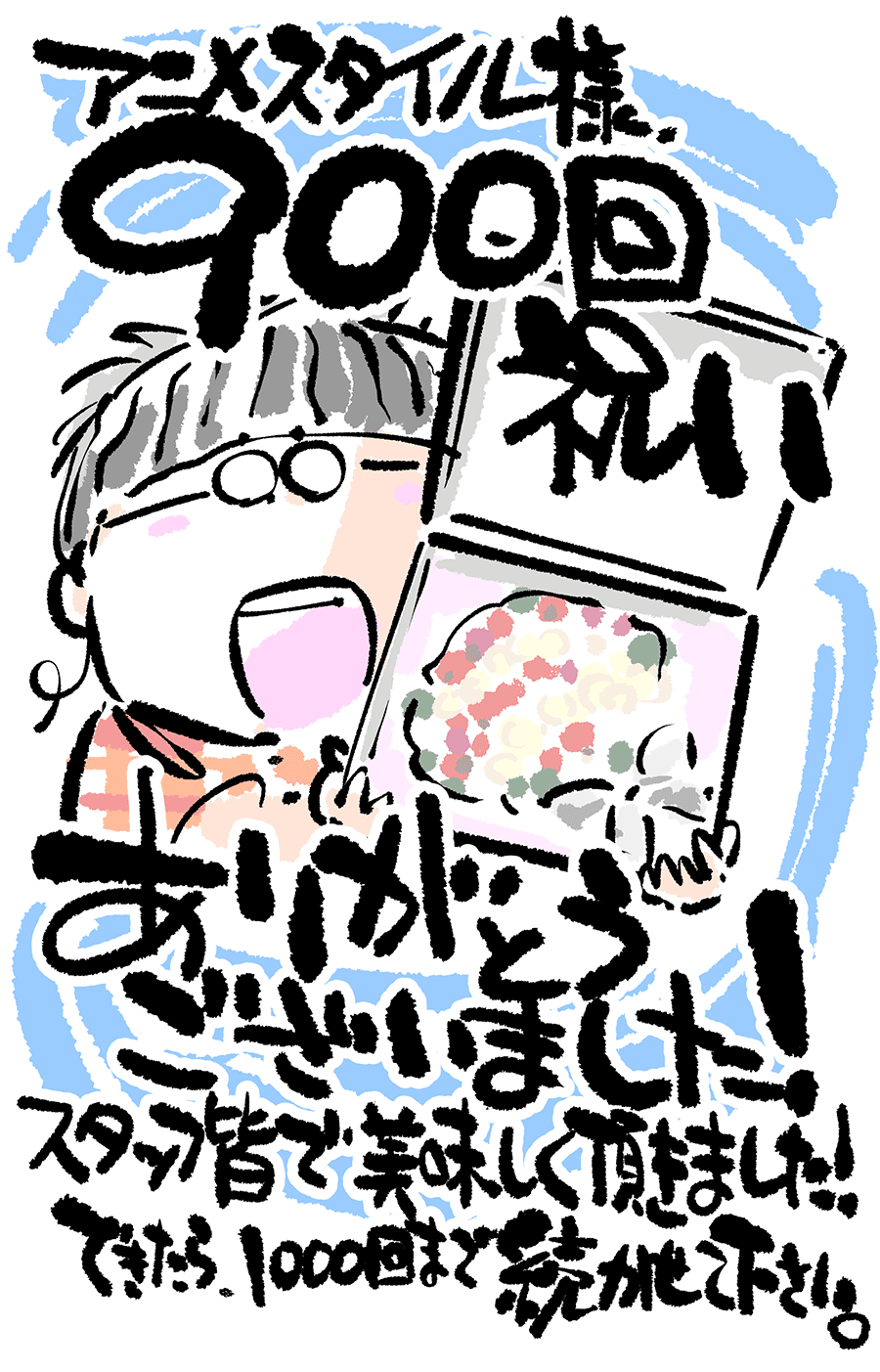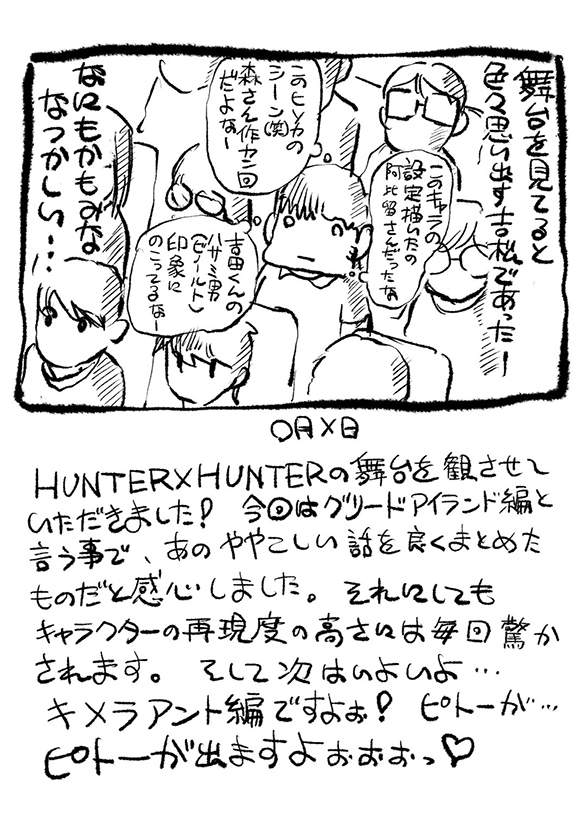腹巻猫です。前回取り上げた『天久鷹央の推理カルテ』に続いて、今回も探偵が活躍するミステリー作品を取り上げたいと思います。6月末で最終回を迎える「小市民シリーズ」です。こちらは高校生探偵が活躍する青春ミステリー。一風変わった音楽と音楽演出が特徴です。
「小市民シリーズ」は米澤穂信のミステリー小説を原作に、監督・神戸守、アニメーション制作・ラパントラックのスタッフで制作されたTVアニメ。第1期(第1話〜第10話)が2024年7月から9月まで、第2期(第11話〜第22話)が2025年4月から6月まで放映された。
小鳩常悟朗と小佐内ゆきは、人並はずれた推理力と洞察力を持ちながら、平凡な日常にあこがれて「小市民」をめざす高校生。2人は中学時代に関わった事件の苦い体験から、探偵のようにふるまうことをやめ、「小市民」として生きることを選んだのだ。しかし、2人は新たな事件に巻き込まれ、謎を解かざるをえなくなってしまう。
小鳩と小佐内は、恋人とも友人とも異なる「互恵関係」を結んでいる。2人は協力しあうこともあれば、互いに秘密で行動することもある。その微妙な関係が緊張感を生む。事件を通して2人の関係が徐々に変化していくのが、青春ミステリーらしい味わいになっている。
アニメ版では小説ではできない独特の演出が見られる。小鳩と小佐内が話をしていると、突然背景が変わり、2人のいる場所が移動したように見えることがある。しかし、それは一種の心象風景で、実際は移動していないのだ。視覚的な変化をつけることでセリフの多いシーンを飽きさせずに見せ、同時に言葉の裏にある感情を表現しているのだろう。
音楽演出にも特徴がある。前回取り上げた『天久鷹央の推理カルテ』で1話あたりの使用曲数が少ないという話をしたが、本作はそれに輪をかけて少ない。1話あたり2〜6曲くらい。音楽が少ないぶんセリフと画面に集中することになる。そして音楽が流れると、特にドラマティックなシーンでなくても「何かが起こっている」という気分になる。これも小説ではできない演出である。
音楽(劇伴)はTVアニメ『約束のネバーランド』『ニンジャラ』等の劇伴を手がける小畑貴裕が担当。『約束のネバーランド』も「小市民シリーズ」と同じ神戸守監督作品だった。
月刊Newtypeの2024年9月号に神戸監督と小畑貴裕が本作について語るインタビューが掲載されている。以下、そのインタビューを参考に本作の音楽を読み解いてみよう。
神戸監督から小畑には「舞台は岐阜の郊外ののどかなイメージだけど、音楽には少しとがった要素がほしい」とオーダーがあったという。そこで小畑は、日常感を重視しつつも、特徴のある音を取り入れて音楽を作っていった。
具体的には、さまざまな民族楽器が使われている。アイルランドのティン・ホイッスル、フィドル、イタリアのオカリナ、マンドリン、12弦ギターなど。ファンタジー系の作品で使われるような楽器が日常描写や情景描写に使われ、地方都市の素朴な風景にふしぎな味わいを加えている。作曲にあたり、小畑は物語の舞台になった土地(岐阜)まで足を運んで、現地の空気感を参考にしたそうだ。
女声ボーカルが入る曲も印象的だ。その代表が本作のメインテーマである「小市民シリーズMain Theme」という曲。神戸監督はもともと、歌詞のついた曲をいくつか作り、それを推理シーンに流すことを考えていたという。しかし、小畑が作った最初のデモがすごくよかったので、それ1曲でいこうということになったそうだ。
ほかにも、曲によっては変拍子を入れたり、あるべき拍子を1拍抜いたりといった、すぐには気づかないけれどなんとなく違和感を感じるような工夫がほどこされている。
音楽演出の特徴としては、先述したとおり、1話あたりの曲数が少ないことが挙げられる。神戸監督から小畑には「この作品ではあまり音楽を使わない。だけど、使いたいシーンではフル尺で使いたい」と話があったそうだ。神戸監督は第1話のクライマックスにメインテーマを流そうと決め、そこから逆算して絵コンテを切っていったという。音楽を限定して使うことで最大限の効果を上げようとしたことがうかがえるエピソードである。
もうひとつ、スイーツを食べるシーンが多い本作ならではの試みがある。カフェやレストランで流れるBGM、つまり現実音楽を演出に取り入れていることだ。小鳩と小佐内がスイーツを食べながら話をするシーンでは店内のBGMがずっと流れている。それらはすべて小畑貴裕のオリジナル曲で、場面に合わせて選曲されている。目立たないように流れている店内BGMだけど、シーンの雰囲気をコントロールし、2人の会話にほのかな色づけをする役割を果たしているのだ。
本作のサウンドトラック・アルバムは、2025年6月18日に「TVアニメ『小市民シリーズ』オリジナル・サウンドトラック」のタイトルでバップからリリースされた。CDと配信があり、CDは2枚組。
収録曲は以下のとおり。
ディスク1
1-01.小市民シリーズMain Theme
1-02.キュートな小佐内さん
1-03.復讐
1-04.ミステリアス
1-05.捜査
1-06.推理する小鳩常悟朗
1-07.謎解き
1-08.おいしいココアの作り方
1-09.推察
1-10.二人の日常
1-11.フラッシュバック
1-12.スイート・メモリー
1-13.静かな景色
1-14.のどかな街並み
1-15.さて、ケーキを食べよう
1-16.忍び寄る不安
1-17.緊迫
1-18.約束のいちごタルト
1-19.ハンプティ・ダンプティ
1-20.Bittersweet
1-21.泣きながら、タンメン
1-22.泣きながら、タンメン (No Vocal ver.)
1-23.トロピカルパフェ
1-24.スイーツ巡り
1-25.Race Against The Clock
1-26.小市民シリーズMain Theme (pf ver.)
ディスク2
2-01.小市民シリーズMain Theme (inst ver.)
2-02.不審火
2-03.夜のパトロール
2-04.瓜野のプライド
2-05.瓜野の決意
2-06.小市民シリーズMain Theme (Major ver.)
2-07.My Home Town
2-08.メイルシュトロム
2-09.Four Season
2-10.逃避
2-11.独白
2-12.小市民シリーズMain Theme (Gt ver.)
2枚に分けて劇伴38曲を収録。主題歌は収録していない。
ディスク1が第1期で作られた曲、ディスク2が第2期用に作られた曲(メインテーマを除く)という構成。おそらくこれで全曲である。通常のTVアニメの曲数(40〜50曲)と比べて極端に少ないことがわかる。しかも、この中には劇伴として使われた曲だけでなく、店内BGMとして使われた曲も10曲くらい含まれている。
ディスク1から紹介しよう。
1曲目「小市民シリーズMain Theme」は本作のメインテーマ。アコースティックギターとフィドルによる前奏から始まり、ユリカリパブリックが歌うメロディに展開する。劇伴でありながら、歌詞のついた歌でもあるという曲。第1話のクライマックス、といっても小鳩と小佐内が会話するだけのシーンに流れて、2人の関係を印象づけていた。1期の最終回(第10話)で2人が互恵関係を解消しようと話し合うシーンに流れたのもこの曲。第2期の最終回(第22話)のラストシーンも同じ曲で締めくくられた。
メインテーマのバリエーションには、ボーカルを笛に置き換えたインスト・バージョン(inst ver.)、ピアノ・バージョン(pf ver.)、ギター・バージョン(Gt ver.)、メジャー・バージョン(Major ver.)がある。インスト・バージョンは第8話と第10話で、ピアノ・バージョンは第10話と第21話で、ギター・バージョンは第15話で、メジャー・バージョンは第17話で使用された。メインテーマのフレーズは変形されて、ほかの曲にも引用されている。
2曲目「キュートな小佐内さん」と3曲目「復讐」は小佐内ゆきのテーマ。どちらもメインテーマの変形だ。小佐内の少女っぽい風貌を表現するのがピチカートやビブラフォンの音色を使った「キュートな小佐内さん」。心の内にある狼のような一面を表現するのが「復讐」。「復讐」は2本のチェロの旋律を重ねて小佐内の2面性を表現した曲だ。第9話で小佐内が誘拐事件の背景を小鳩に話す場面に流れていた。
「ミステリアス」(トラック4)、「捜査」(トラック5)、「おいしいココアの作り方」(トラック8)、「推察」(トラック9)などは、小鳩と小佐内が謎を解こうとする場面によく使われた曲。シンプルな構成ながら、ゆれるリズムと民族楽器の音色などでミステリーっぽい雰囲気をかもし出している。「おいしいココアの作り方」は、第2話で小鳩がココアの作り方をシミュレーションする場面に流れていた。
「推理する小鳩常悟朗」(トラック6)と「謎解き」(トラック7)は小鳩常悟朗のテーマ。これもメインテーマの変形だ。曲名通り、小鳩が推理する場面などに使われている。
笛の音がさわやかな「二人の日常」(トラック10)を挟んで、「フラッシュバック」(トラック11)と「スイート・メモリー」(トラック12)は小鳩と小佐内の心情を描写する重要曲。メランコリックなチェロのメロディによる「フラッシュバック」は第1期後半のエピソード『夏期限定トロピカルパフェ事件』で小鳩と小佐内が事件をふり返るシーン(第9話、10話)に使われた。第2期では2人が中学生のときに関わった事件を回想する場面でも流れている。女声ボーカルがしっとり歌う「スイート・メモリー」は第10話で2人が互恵関係を解消したあと、小佐内が雨の中を赤い傘をさして帰っていく切ない場面に使用。メインテーマの変奏である。憂いをたたえた曲調が2人の胸に秘めた想いを代弁しているようだ。
ほっとひと息つく日常シーンに流れた3曲(「静かな景色」「のどかな街並み」「さて、ケーキを食べよう」)を挟んで、サスペンス描写曲が登場する。
「忍び寄る不安」(トラック16)と「緊迫」(トラック17)は小鳩と小佐内の動揺や憤りを表現する曲としてしばしば使われた前衛ジャズ風の曲。第1期後半で描かれる誘拐事件にからんで使用されたのが記憶に残る。「緊迫」では、低くうなるようなバスクラリネットの音が効果を上げている。
収録位置は離れるが、トラック25の「Race Against The Clock(時間との競争)」もサスペンス描写曲のひとつ。本作には珍しい、ストレートに焦燥感や緊迫感をあおるタイプの曲である。第4話で小佐内と連絡が取れないことを心配した小鳩がバスに乗って駆けつけようとする場面が唯一の使用だった。
ディスク1で残った7曲、トラック18「約束のいちこタルト」〜トラック24「スイーツ巡り」は、いずれも飲食店や商店街などで流れるBGMとして使用された曲である。ピアノ、ドラムス、ウッドベースのピアノトリオのスタイルで作られた「Bittersweet」はジャズ出身の小畑らしい曲。ピアノも小畑が弾いている。堤田ともこが歌う演歌「泣きながら、タンメン」が異色だが、これは商店街やラーメン屋で流れている曲。街ではおなじみのヒット曲らしく、いろんな場所でこの歌が聴こえてくる。
ディスク2も簡単に紹介しよう。
トラック2「不審火」〜トラック5「瓜野の決意」は、第2期前半の『秋期限定栗きんとん事件』のエピソードで使われた曲。小佐内にいいところを見せようとする新聞部の1年生・瓜野のための曲が作られているのが特徴だ。
トラック6の「小市民シリーズMain Theme (Major ver.)」は、第17話で小鳩と小佐内が一度解消した互恵関係を復活させる場面に使用。主旋律をメジャーに転調して使うアイデアが効いている。
続いて収録された3曲、「My Home Town」(トラック7)、「メイルシュトロム」(トラック8)、「Four Season」(トラック9)は、いずれも飲食店やホテルのラウンジで流れるBGMとして使われた曲。ちなみに「ハンプティ・ダンプティ」も「メイルシュトロム」も店の名前なのだ。
「逃避」(トラック10)と「独白」(トラック11)の2曲は、第2期後半のエピソード「冬期限定ボンボンショコラ事件」のために用意された曲。前衛ジャズ風の「逃避」ではバスクラリネットと弦が不穏な調べを奏で、「独白」は弦楽器と笛が哀感を帯びたメロディを聴かせる。物語の大詰めとなる第21話と第22話で使用された。
『小市民シリーズ』の音楽の大半は、一聴すると、そんなに変わった音楽には聞こえない。けれど、よく聴くと使われている楽器や演奏法、リズムやメロディの崩し方などに独特の工夫がある。日常に溶け込みながら、じわじわと日常を異化していくような、スリリングな要素を秘めた音楽である。そんな音楽の中で憩いとなるのが、店内BGM用に書かれた軽快な曲や優雅な曲なのだが、劇中では、その曲をバックにおだやかでない会話が交わされる。小市民にあこがれても小市民になりきれない小鳩と小佐内の屈折が、音楽と音楽演出にも反映されているのだ。劇中の小佐内ゆきは羊の着ぐるみで狼の本性を隠した少女のように描かれているが、このサントラも、羊のような親しみやすさの裏にとがった牙を隠した音楽である。
TVアニメ『小市民シリーズ』オリジナル・サウンドトラック
Amazon