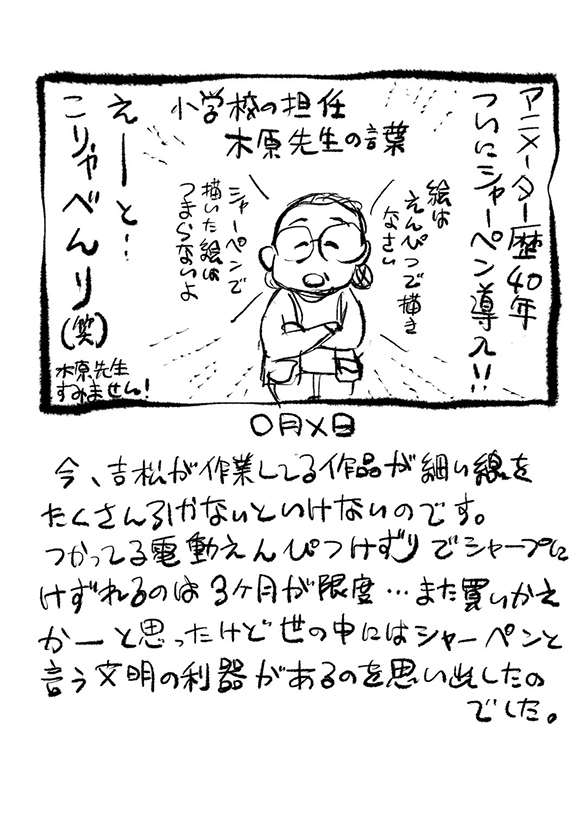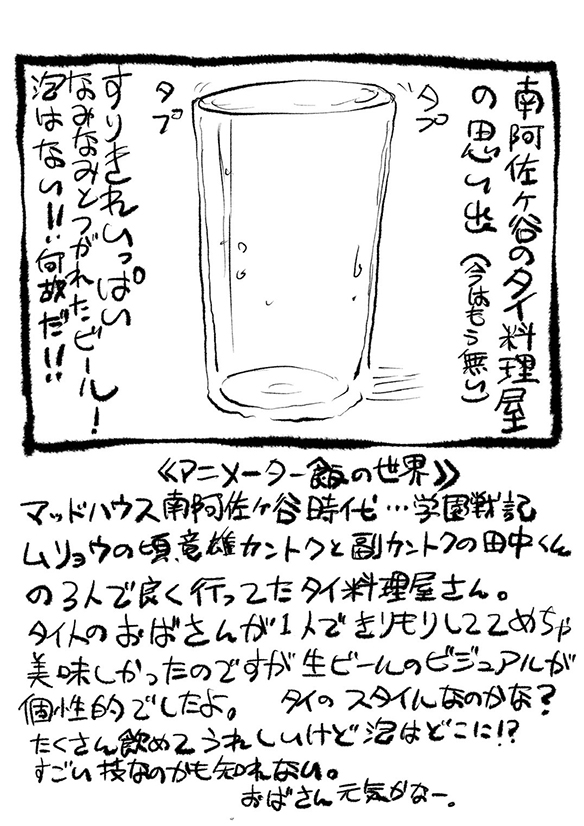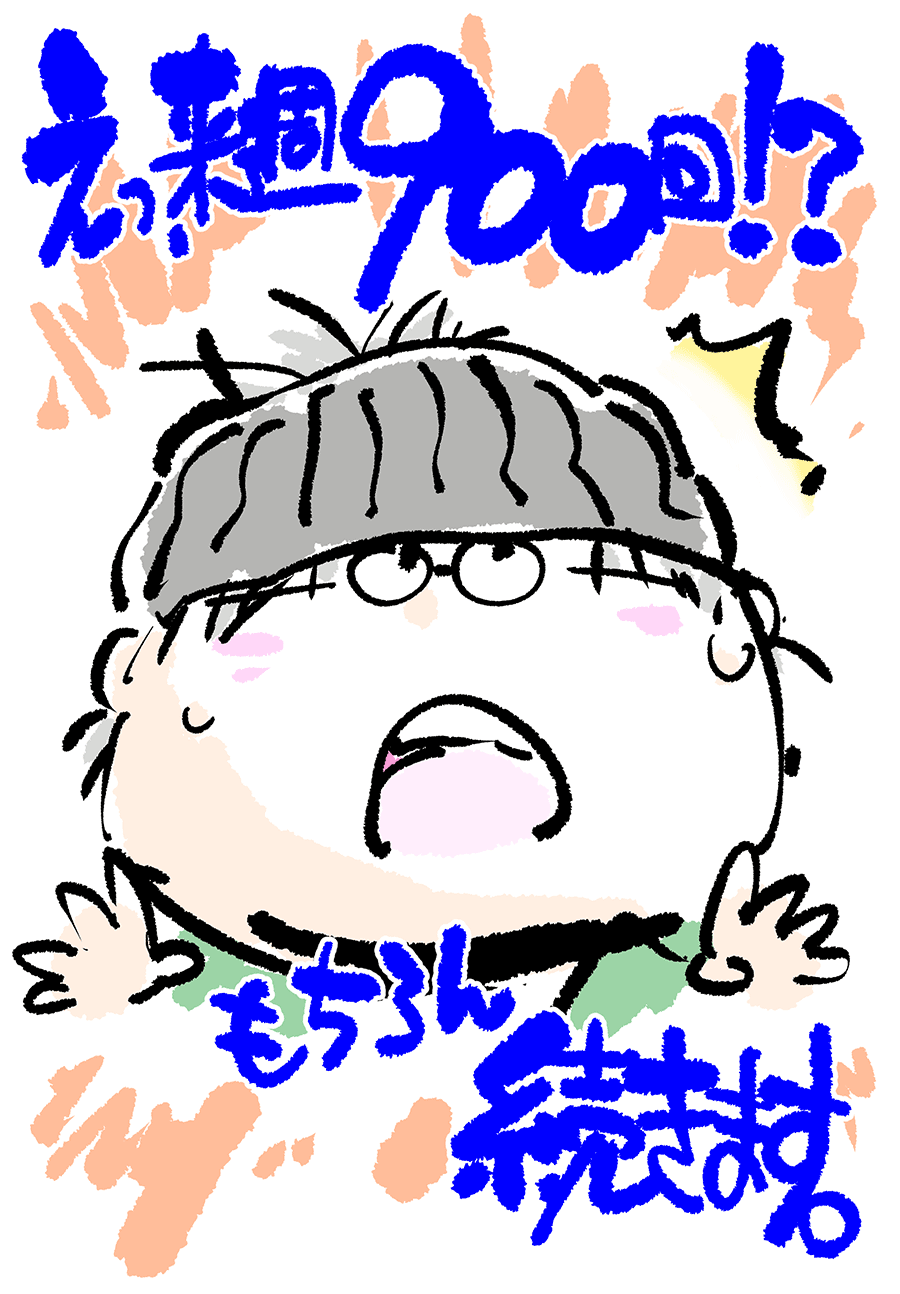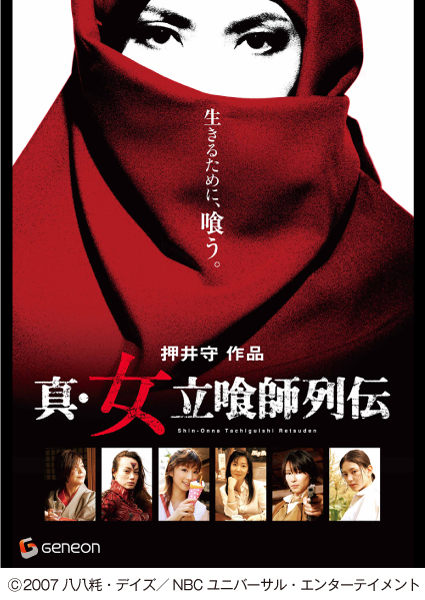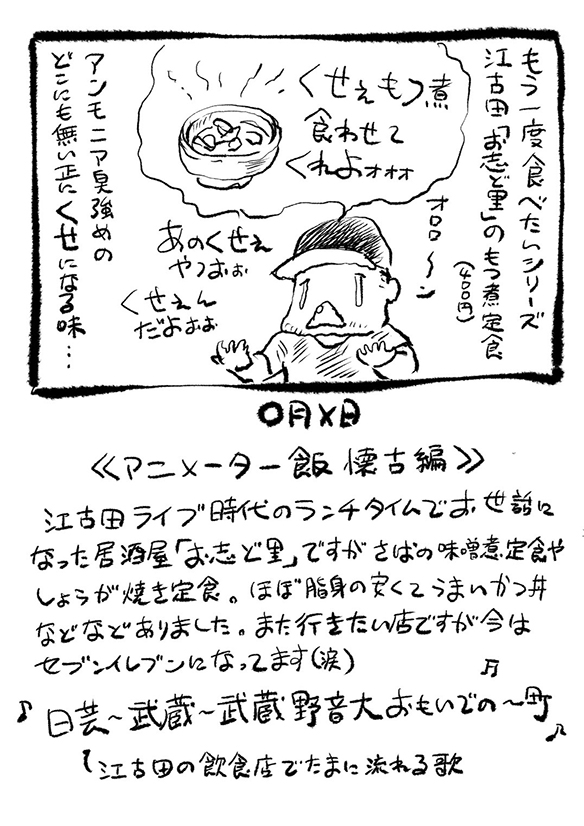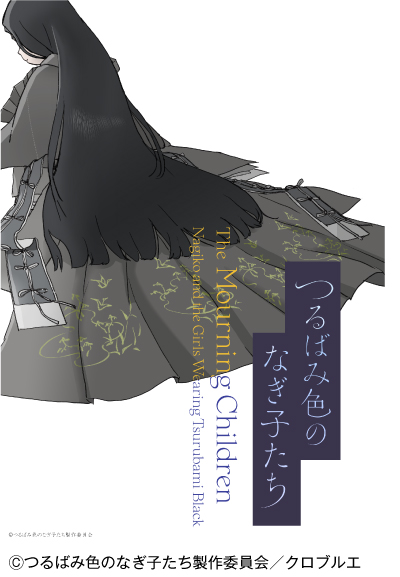もり 僕は『らんま』でディーンに出向になって、亜細亜堂に戻ってないんですよ。ぴえろに行って、小林(治)さんが断った『江戸っ子ボーイ がってん太助』で監督をやって。ディーンからガイナックスに行って『ふしぎの海のナディア』をやって。で、その途中でフリーになっちゃったから。
本郷 戻っていない?
もり 戻ってないです。ぴえろやガイナで仕事をしていても、芝山さんと仕事をした事が役に立っているというか。例えばガイナックスで鈴木俊二さんとか、鶴巻和哉君とか、本田雄君とか、あの辺と会った時に「あ、こいつらすげえ」って思えるくらいの目は養わせてもらったかなと。
本郷 うんうん。
もり 芝山さんに教えてもらった事の一部ですけど、『ど根性ガエル』的なタイミングをガイナの連中と共有できた事とか、そういうのは有意義だったかなあと。
本郷 その後で芝山さんと仕事をご一緒するのは『まじめにふまじめ かいけつゾロリ』ですか。
もり そうです。『ゾロリ』の3年目で、2006年ですね(編注:『まじめにふまじめ かいけつゾロリ』の第51話から芝山努が総監督、加瀬充子が監督、もりたけしがシリーズ構成となった。前シリーズ『かいけつゾロリ』から数えて3年目)。
本郷 そこまでは芝山さんとの接点がなかった?
もり ほぼないです。
本郷 『ゾロリ』にはどうして参加する事になったんですか。亜細亜堂から声が掛かった? 岡村(雅裕)さんから?
もり そう。ここで、です。ここ(池袋の喫茶店)に呼び出されて(笑)。
本郷 ここ? まさに?
もり ここに。僕が亜細亜堂を辞めた時は円満退社なかたちになっていて、『(秘境探検)ファム&イーリー』の監督でも呼び出されているので。
本郷 なるほど。『ゾロリ』のシリーズ構成というのはどういうかたちだったんですか。
もり 自分が参加する前の段階で、原作は使いきっていて、3年目は全話、オリジナルの話を考えなくてはいけなかったんです。僕は「話を考えて」と、岡村さんに言われたんですよ。脚本打ち合わせには原作者の原ゆたか先生も参加していて、原先生と話をしながら脚本作りを進めました。
本郷 芝山さんはどういった立場で参加されていたんですか。
もり 肩書は総監督でした。話は僕が考えてるから、原作とトーンが違ったりとか、温度差があったりするんですよ。それについて原先生が「これはどうなの?」と聞いてくるんです。そうなると、紛糾はしないんですけど、会議が長引くんですよね。
本郷 まあそうですね。
もり 芝山さんが2話目3話目ぐらいから、シナリオの第1稿の端とか余白に画を描いてきてくれるようになったんです。イメージボード的なものを。
本郷 私は見た事あるけど、滅茶苦茶上手な画でしたよね(編注:その一部が『まじめにふまじめ かいけつゾロリ』のムックに掲載されている)。
もり そうなんです。それを持ってきてくださる。それを見ると、原先生もすぐにやる事を理解して「ああ、はいはい」と言ってくれる。途中から原先生が、芝山さんの画を楽しみにするようになっちゃって。だから、本当に芝山さんに助けていただきました。話の内容云々じゃなくて、芝山さんの画の説得力。
本郷 3年目は52本あったんですか。
もり ほぼ1年やりました。
本郷 その1年分で芝山さんが。
もり ほぼ全部で。
本郷 毎回1枚か2枚の画を描いてた?
もり 1枚2枚どころじゃないですよ。多いと十数点。
本郷 単純に言うと500枚近くを描いたんだ。
もり そうですね。シーンに合わせてのイメージボードですから、美術設定も兼ねているんですよ。例えばシナリオに「消防署前」があると、昭和の消防署を何も見ないで描いちゃう。
本郷 芝山さんって見ないで描いちゃうんだよねえ。
もり 「芝山さん、なんでこんなの描けるんですか」と聞くと、「いやあ、なんとなく覚えてるからさ」って。
本郷 凄いよねえ。
もり 例えば、奥にパースがある住宅街の設定というと、奥に消失点があって一本線じゃないですか。
本郷 うんうん。
もり 道は本来なら曲がってるし、起伏もある筈なんです。芝山さんの描かれる画って、そういうところも再現してるんですよね。芝山さんの描かれる画って「どこかの写真をなぞったの?」と思うくらいリアルなんですよね。起伏とか、傾き方とか。
本郷 芝山さんの目を通して作ってあるから、もの凄い画としての説得力があるっていうのはある気がする。
もり そういうところは、やっぱり宮崎さんと被るというか。これを言うと怒られるかもしれないですが。
本郷 そういう事ができたのは、あの2人しかいないかもしれない。
もり いないですね。自分らの世代で同じような事を思ったのは、前田真宏氏ぐらいですね。彼は凄い。
本郷 らしいですね。
もり 彼も本当に脳内の引き出しで画が描けちゃう人なので。自分が見た中で凄いと思ったのは、宮崎さんと芝山さんと前田真宏さん。天才っていう言葉って、そういう人達の為にあるんだろうなとは思うんですよ。
本郷 だから全話じゃないけど、『ガンバの冒険』のレイアウトをシリーズ通じて1人で描いたとか。普通の人間がその仕事量はこなせないじゃない? 宮崎駿さんが『アルプスの少女ハイジ』と『母をたずねて三千里』で全話のレイアウトを描いていて、その後は誰も続かないわけで。そういう人達がいたおかげで、日本のアニメの礎が作られたというのはあると思うし。
もり 芝山さんがやられた『ガンバの冒険』で、どこかの家の縁の下の描写だったと思うんですが、BOOK3枚の置き換えで回り込みをやってるんですよね。それをパクろうと思って『ナディア』で大失敗して、庵野(秀明)さんに失笑された事がありますけど。
本郷 望月(智充)さんもやったよね。
もり そうそう。で、望月さんと話をしたら「オレも失敗したんだよ!」と言っていて。
本郷 ところで、芝山さんの作打ちって、見た事ありますか。
もり 1回だけあります。さっき話題にした「とんぼのやどり木」です。それから、自分が参加した打ち合わせではないですけど、端で聞いてた事はありますよ。
本郷 自分は『伊賀野カバ丸』とか『昔ばなし』。芝山さん以外の、他の演出の作打ちって見た事ないから、芝山さんの猿真似で作打ちをやっていたんです。
芝山さんって、声色を使い分けて「なんだよのび太!」「いい加減にしろよのび太」「のび太さーん」とキャラクターのセリフを読み上げるじゃない。作打ちってそうやるもんだと思ってやっていたんだけど、ある時に「なんで亜細亜堂の人は声色使って、作打ちをやるんですか」と言われて(笑)。それで「みんなこれでやっているわけではないんだ」と思ったんです。
もり 僕は小林さんのグループだったから、小林さん的な打ち合わせになりますね。
本郷 ああ、そうかそうか。小林さんは声色使わない?
もり 使わないです。
本郷 ああそうか。他の人の作打ちを見た事ないから、本当に、そういうのが作打ちだと思ってて。
もり 2大師匠の2人のうち、僕が直接仕事してたのは小林治さんなんです。『オレンジ★ロード』と『燃える!お兄さん』をやっていましたから。
本郷 話を戻すと、『ゾロリ』の流れで2007年にオリジナルのWEB小説「サンタクルーズ」を発表されるんですね。
もり はい。『ゾロリ』で距離が近くなった時に、たまたま「トルネードベース」(編注:2006年にスタートしたWEBマガジン。2008年まで更新されていた)に小説を掲載させていただく事になったので、ダメ元で芝山さんにおねだりをしたんです。岡村さんに『ゾロリ』で恩を売っていたので(笑)、岡村さんを通して頼んだら、芝山さんは「いいよ」って引き受けてくださった。
本郷 それは今でも読めるんですか。
もり もう読めないです。一応、原稿はありますし、芝山さんが描いてくださった画のデータは残してあって。
本郷 じゃあ、芝山さんの画集が出るのだったら、掲載されるといいかもしれないですね。
もり 勿論、勿論。私のところにデータがあります。
本郷 で、その時は注文とか付けたんですか。
もり なんにも付けてないです。「こういうものを書いたので、大変恐縮なんですけど、イラストを描いていただけませんか」というかたちでお願いしました。「どこの画がほしいとかないの?」と聞かれたので、芝山さんが思い付いたところを描いてくださいと言ったんですよ。そしたら、場面としては本当に的確に、さらに望んだ以上に格好いい画を描いていただいて。
本郷 本当、きちんと読める絵物語としては、芝山さんの仕事の中ではレアな部分だと思いますけど。
もり 本当に感謝してますよ。
本郷 その後は、2012年と2013年の『まじめにふまじめ かいけつゾロリ』の映画の脚本というかたちになる?
もり その時は、もう芝山さんは関わられてないです。
本郷 あ、そうなんですか。
もり あの時は監督も加瀬さんから岩崎知子さんに代わって。で、僕が呼ばれてシナリオ、最初の2本か3本かな。
本郷 2012年の『映画かいけつゾロリ だ・だ・だ・だいぼうけん!』には監修の役職で芝山さんの名前が出てるけど、実質は。
もり 名前は出てますけど、ほぼやってないです。
本郷 じゃあ、最後に芝山さんと関わったのは「サンタクルーズ」。
もり そうです。その後は仕事では関わってないですね。
本郷 その後に会ったのは芝山さんを囲む会ですか。師匠を囲む会は何回ぐらいやったのかな、4~5回やったのかな。
もり そうですね、4~5回やってますね。本郷さんのお声掛けのおかげで、やっと芝山さんが僕らに心を開いてくれた。
本郷 そうかもね(笑)。ちょっと嬉しかったんだろうね。
もり でね、それまではやっぱり上司と部下だったんだけど。
本郷 そうだね。距離感があった。
もり やっと認めていただいたというか。酔っ払わせて、無理やり我々が。
本郷 本音を吐かせた(笑)。
もり そうそう。本音を吐かせたり。それから無理やり弟子認定をしていただいたりとか。「僕らが弟子って事でよろしいですね?」と言って、「分かった。お前ら全員弟子だ」という言質をいただいてるとかね。
本郷 亜細亜堂を辞めたばっかりの時のシンエイの忘年会があって。大勢でワアワアやっている時、テレ朝のプロデューサーに「本郷ちゃんってオカマなの?」と言われたんですよ。「違いますけど」と答えたら「芝山さんが今来てさ、あいつは裏切り者でオカマだって言ってたよ」って。
もり 浅草の人だから口が悪いんですね。
本郷 だけど、それがちょっと嬉しかったね。認めてくれたから悪口を言ってくれるみたいな。どうでもいいなら言わないじゃない? その師匠の会を何回かやった時に、芝山さんが「本郷君はオレに似てるね。口の悪いところが」と言ったんです。「そこだけかい!」と思って。でも、ちょっと嬉しかった。
もり はいはい。
本郷 やっぱり洒落てるんだよね、全体的に。
もり だから、粋な方だと思う。
本郷 そうだよね。あんまり人間関係をベタベタさせない。全部仕事で結果を出す。何十年にも渡って亜細亜堂を支えていたわけじゃない?
もり そうですよね。売上の大半を芝山さんが出してたわけだから。
本郷 芝山さんが仕事を決めてきて、その仕事をみんなに分配する。芝山さんに「なんでそんなに沢山できるんですか」と聞いた事があるんだけど「責任があるからだよ」と言われた(笑)。
もり (笑)。僕はゴンゾの時代に似たような事を少しやりましたけど、無理ですね。芝山さんみたいにはできない。
本郷 普通の人なら「それが自分にとってなんのメリットがある?」と考えちゃうじゃない。だけど、芝山さんは何十年にも渡ってやった。自分がまだ亜細亜堂にいた頃の事だけど、「芝山さん、これもお願いします」「これもお願いします」と仕事を積まれた後、芝山さんの「なんでもかんでもオレがやれるってものじゃないんだよ」という独り言が聞こえた事があった。芝山さんでもきついんだって思いました。
もり いや、だって凄い仕事量ですから。自分は足元にも及ばないぐらいです。僕は亜細亜堂時代に5本掛け持ちとかした事がありました。大晦日に家に帰れず、熱を出して、元旦を亜細亜堂の2スタの奥の部屋で迎えた事がありましたけど、あの時の自分よりも仕事してますからね。芝山さんがあの仕事量を実現させていたのは即断即決ですね。
本郷 そうそう、それだね。
もり 即断即決って言葉を芝山さんから学びましたね。「プロは即断即決」って。
本郷 前に大武(正枝)さんに聞いた時もその話が出たんだけど、芝山さんって、迷ってる時間がないんだよね。机に座った瞬間に描き始める。普通の人って座ったところで「はあ~」とか「ふう~」とか、そういう時間があるんだけど、座った瞬間に手を動かしてて止まらないのが凄いよね。
もり 近くの席で仕事をしていた頃にも感じていました。それが気配で分かるんですよ。姿は見えてないけど、ず~っとそこにいて手を動かしているのが分かる。
本郷 手を動かしてる。
もり あれは恐怖ですよ、本当に。
本郷 ああいう人は、他に見た事がないなあ。
もり 怠けられないっていうか。
本郷 近くにいたらね。
もり 近くにいる他のベテランはのんびり仕事をしてるんですけどね(笑)。
本郷 芝山さんは他の人が自分と同じようにはできないっていう事を表面上は気にしてないよね。
もり 芝山さんの自慢的なトークってあまり聞いた事がないんですが、『狼少年ケン』の時に一晩で900枚描いたと聞いた事があります。
本郷 (笑)。
もり 一発描きで全部描いているから。
本郷 一発描きだろうね。
もり だけど、900ってどういう数だろうと思いますけど。
本郷 まあ、早いんだろうね。やっぱり巧くて早い人って描く画が見えてて、なぞるに近い。
もり それも言われてましたよね。「どうしたら描けるんですか」「いやあ、見えてるから、それをなぞってるんだよ」って。
本郷 『ドラえもん』の劇場を20作ぐらい、毎年、ほぼ1人でコンテをやっていたでしょ。
もり 表紙は描かなくていいのに、表紙の為にすげえ画を描いてるし。
本郷 そうそう。表紙の為に凝った画を描いている。それも洒落てるんだよね。端からだと余裕があるように見えるようにやってるというか。
もり 芝山さんが「オレの仕事はコンテが一番いいんだ」と言った事があるんです。「お前らが寄ってたかってひどいものにしてる」っていう。
本郷 芝山さんが酔っ払った時に、私もそれを聞きました。「みんなで寄ってたかって、オレのコンテをダメにしやがって」と言っていた。
もり その一言に尽きますよね。本当はそう思っているんだけど、普段は口に出さない。
本郷 芝山さんが、どこかの出版社のアニメとは関係ない編集部に依頼されてイラストを描いて、それで「あなたの画は冷たい」と言われたんです。それで凄く怒ってたのは覚えてるんだよね。
もり (笑)。
本郷 だけど、分かるところもあるんです。画に情念みたいなのを入れる事ってありますよね。小林さんはまさに情念の人じゃない。芝山さんって、それを入れたくないタイプなので。
もり 照れ屋さんなんですね。
本郷 そうそう。
もり 分かります。
本郷 気持ちは熱いし、嫉妬深いところもあるんだけど、それを気取られないようにしている。それが格好よさだと思っているところがあると思う。
もり だから小林さんとペアだったんじゃないですか。
本郷 そうだね。対になってるんだよね。2人とも小林さんタイプだったら、大喧嘩するよね。
もり そうそう。すぐに決別してる。
本郷 決別してるよね。一時期、藤子不二雄的なノリで、亜細亜堂って芝山さんと小林さんがコンビでやっていて。
もり 『ど根性ガエル』ではひとつのエピソードを前半と後半で分けて、「せーの」でそれぞれが描いてたって聞きましたからね。
本郷 亜細亜堂というペンネームでやっていた時はそうだったらしいよ。『昔ばなし』をやっていた時も、シナリオを半分ずつ持って帰って、家でやって合わせたと言ってたよ。
もり 『昔ばなし』で思い出しましたけど。「枚数使いすぎ」問題が亜細亜堂で勃発した事があるんです。それが小林さんの逆鱗に触れて。
本郷 ああ(笑)。
もり その時に芝山さんが、500枚で『昔ばなし』を作ったんです。カメラワークを駆使して。ほとんど止めスライドで、500枚でやりきりましたからね。その時にカメラワークで見せるっていう手法は、自分の中で残りましたよ。
本郷 小林さんはそう言うけど、自分が『昔ばなし』をやると滅茶苦茶枚数がかかる。
もり すげえかかってましたよ(笑)。
本郷 でも、人が枚数をかけてると怒るんだよ。経営者なので。
もり 小林さんといえばタイミングの付け方も凄いです。
本郷 凄いよね。
もり 「え、こんなところで5コマ使うの!?」っていうのもありましたから。
本郷 芝山さんも小林さんのタイミングを褒めていましたね。私は芝山さんと小林さんの撮出しが一番最初の仕事だったんです。最初にその2人の仕事ぶりを間近で見れたっていうのは凄くよかったと思いますけど。小林さんの話は尺足らずになる事が多くて、10分しかないのに2分足らない事があって、そうしたら小林さんが「全部のカットを2秒ずつ延ばせばいいんだよ」と言って。
もり (笑)。
本郷 芝山さんのはカッチリ作られてて、全部そのまんまでパッケージみたいになってるんだよね。小林さんのは意外とアバウト。
もり 長嶋(茂雄)な感じですよ。
本郷 そうそう。同じ作品をずっとやってた2人なのに、方法論がまったく違うんだよね。あれがやっぱアニメーションの面白いところだなあって。
もり それが亜細亜堂の個性になっていた。
本郷 個性だね。その2人がメインで、あとは河内さん、山田さんがいた。それに加えて須田さんがいた。それが亜細亜堂のスタイルだった事は間違いないですね。
もり そうだと思います。
本郷 芝山さんって『ドラえもん』と『ちびまる子ちゃん』と『忍たま乱太郎』の監督をやっていて、そのどれもが今も続いてるわけじゃないですか。それらの作られたフィルムの時間数はもの凄いものであるわけで。それが世の中に流布されていて、観た人がアニメ好きになっていったというのは絶対にあるわけで。
もり しかも、それらの作品のベースを作られてますからね。作品のマニュアルを最初に作っていて。
本郷 その部分って、世の中ではあまり評価されないんだけど、作品を周回軌道に乗せるっていうのは凄く難しい事だと思うんだよね。
もり 難しい事だと思います。
本郷 芝山さんは職人って言葉が一番合うかもね。
もり 職人ですよね。
本郷 建築で言うと、3階建ての豪華な邸宅を作るんじゃなくて、誰にとっても住みやすい平屋を作るというか。そして、自分を出しすぎず、原作者の作ったものに準じる事ができる。そういう能力がある人なんだと思います。
取材日時/2024年6月14日 取材/本郷みつる 構成/アニメスタイル編集部
●プロフィール
もりたけし。監督、演出家。代表的な監督作品に『ヴァンドレッド』『ストラトス・フォー』『秘境探検ファム&イーリー』等がある。